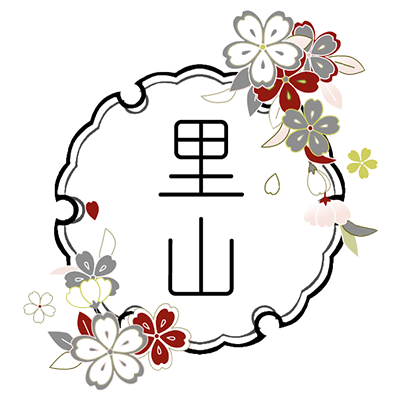発行物紹介
introduction
典ソハ
成人向
朝霧において迷路-まよいみち-
関ヶ原の戦いの一年後に哨戒任務に出た大典太とソハヤ。途中霊に襲われ、ソハヤが攫われてしまう。
なんとか帰ってきたソハヤだが目覚める気配がない。
大典太はソハヤを戻すために、再び関ヶ原の地へと向かう。
シリアス成人向け。
※独自の解釈・審神者・捏造本丸設定が出てきます。
※オリジナルの審神者が出てきて喋ります。名前はありません。
※土佐弁は調べたりコンバータに頼っていますがふんわりしています。
※ゲームにない設定がたくさん出てきます。
※流血・ぬるいホラー・グロ表現があります。
※誤字脱字はあります
イベント頒布価格700円
A5 / 72P
2022年7月24日発行
頒布終了しました
朝霧において迷路-まよいみち- サンプル
SAMPLE
暗く重い、水を湛えた雲が決壊した。ぽつぽつと肌に当たるものに驚いて上を向くよりも先に、それは勢いを増していく。激しさを増すばかりの大粒の雨の中を、雨宿りができる場所を探して駆けた。洞窟を見つけそこに身を滑らすと同時に、雨が堰を切ったように降ってくる。
滑り込んだ洞窟はさほど大きくはないが、一部隊が入って雑魚寝をしても十分なくらいの大きさがあった。奥には腰掛けることのできる大きさの岩もあり、自然にできたものというよりは、人工的に作られた洞窟なのだろう。
「うへぇ」
土砂降りになる前に間に合ってよかったと思っていれば、気の抜けた声が洞窟内に反響した。洞窟の奥、己よりも先に入って行った任務の相方が上げた声に振り向くと、雨に濡れて形を崩した薄い金色の髪をかき上げながら、色を濃くした銀鼠色のジャケットを脱いでいる姿があった。
「間一髪、ってとこだが、それでも結構濡れたな。兄弟も脱いだほうがいいぜ、身体が冷えちまう」
脱いだジャケットを乾かすように振りながらソハヤノツルキが言うのに、大典太光世は同意するように同じ仕立てのジャケットを脱ぐ。秋も深まってきた時分に上着が無いのは少し肌寒い気もしたが、洞窟の中は思っていたよりは暖かかく、ジャケット脱いでもそこまで寒さを感じなかった。壁に立て掛けた刀にジャケットを掛け、持っていた小さな荷物入れの中に入っていた手ぬぐいで濡れた髪や肌を拭いて、できるだけ水気を取る。
「しかし、これは暫く動けそうにないな」
ざぁざぁと激しい雨音の中でもしっかりと耳に届いた言葉に頷く。洞窟の入口から見た外は、まるで霧が出たかのように雨で煙って白い。
「帰城ができんな……」
「だなぁ。こんな雨じゃあ、ゲートを開く場所にまで辿り着かねえ。後は帰城して報告だけだからいいものの、最悪雨が止むまでここから動けない可能性もあるな」
大典太とソハヤは二振りでとある時代へと遠征に来ていた。通常の遠征とは少し違い、現在確認されている時空の歪みが存在する場所以外への哨戒遠征だ。
本丸の運営年数が長くなればなるほど、練度が上限に達し出陣できない刀も増えてくる。政府が余剰戦力と呼ぶ上限に達した刀を哨戒に出し、時間軸の歪みや遡行軍の発見をする仕事を、大典太たちの本丸は数年前から請け負っている。特別報酬が出る上に、本丸で燻っていた練度上限の刀たちも気晴らしができるから一石二鳥だとは主の弁だ。
そうして内番のように組み込まれたその任務に、今日は大典太とソハヤの三池二振りが当たっていた。哨戒を終え、帰城時間になったからと帰城ゲートを開く場所へと向かおうとした矢先に、この大雨だ。
出陣先の天気は予め教えられているが、哨戒先の時間軸の天気は教えてはもらえない。天気という大規模な自然現象を変化させる術は、時間遡行軍も検非違使も、そしてもちろん時の政府も持ってはいない。故にこの雨も政府からは教えられておらず、結果、大典太とソハヤは雨に濡れてしまった。
「……ひとまず、主に報告だな」
「おう」
言いながら荷物入れを漁っていたソハヤが、取り出した連絡装置を起動する。こんな手のひらに収まるような小さな装置一つで、時代も時空も違う本丸にいる主に繋がるというのは不思議なもので、顕現されて長く経っても未だに仕組みはよく解らない。
『どうした?』
短い呼び出し音の後、主が通話に出る。突然の大雨で帰還ゲートまで辿り着けないことを伝えると、すぐに状況を確認してくれる。五分も待たないうちに、大典太たちが居る場所や、ゲートを開く場所付近が空間的に不安定になっていると告げられた。
『雨のせいだろうな。なんかぐらぐらしてるわ』
「まぁこの雨じゃあ、安定しないだろうな」
『雨音、こっちにも聞こえる』
洞窟内に反響している音が、通信を通して主にも聞こえているらしい。激しいな、と小さな呟きがかろうじて聞こえる。
『強行突破でも無理そう?』
「無理だな。道の先が見えねえから迷子になる」
帰城ゲートは、いま大典太たちがいる洞窟から登っていった山の中腹にある。急な坂や獣道を通り抜けるため、この雨で進むのは危険だろう。
出陣と帰還を行うゲートを開ける場所は限られている。また、時間を遡行するため座標を固定する必要があり、通常は場所も動かすことはできない。移動式の子機を使えばある程度任意の場所からの帰還ができるらしいが、大典太たちの本丸では導入していない。
雨でゲート展開予定地まで辿り着けず、辿り着けたとしてもゲートは不安定。雨が止んで空間が安定するのはいつになるかは分からず、この場所にゲートを繋ぐこともできない。完全に詰みだ。
『そっちの状況は判った。とりあえず報告を聞いてから考えよう』
「了解」
ソハヤは機械に向かって、今日の哨戒任務で得た情報を報告していく。
今日の任務地として政府に指定された時代は、安土桃山の末期、戦国の関ヶ原。かの天下分け目の大いくさが行われた場所だ。戦から一年ほど過ぎた秋の町は、歴史を変えるほどの戦いがあったとは思えないほど長閑だった。彼方此方に戦の名残があり、暮らしぶりは良いものではなかったが、稲穂が揺れる農村特有の長閑さがあった。違和感があればすぐに報告しろと言われていたが、特に歴史を覆すようなことになる点はなくおかしな気配もない。行き交う人々の話を盗み聞いたり、休憩中の農夫にソハヤがそれとなく話を聞いてみたりしたが、変わったことも起きていないようだった。
大典太とソハヤが見てきた関ヶ原の地は、少なくとも政府が気にするようなものはなにもなかった。
『なにもなし、と。……とりあえずそちらには現状把握できる驚異は存在しない、ってことだよな』
「現時点では、な」
『政府から貰った特別札は?』
このような政府からの依頼で歴史上の時間軸に赴く場合、任務開始前に現地の人間に怪しまれないようにするために、認識阻害の札をもらう。更に己たち三池や一部の刀には、霊力等の「人ならざるもの」の気配を消す効果が足された札が渡される。特に大典太は強い霊力が周りにどう影響するかわからないということで、ソハヤのものよりも術が強化された霊力遮断の札を貰っている。霊力遮断の札は外から分からなくするだけでなく、内から外に漏れる霊力も抑えてくれる便利な札だ。緊急時にはこの札を手順に則って破れば霊力を使うこともできる。
「ちゃんとあるぜ。戦闘とかもなかったし、綺麗なままだ」
「ああ」
大典太とソハヤが取り出した札を確認しあってから答えると、審神者は通信の向こうで少し考えるように間をおいてから、じゃあ問題ないかな、と呟く。
『報告も受け取ったし、ここで任務は一旦終了にしよう。二振りは雨が止んでゲートが繋がるまで、そちらで待機してて。もし日没時間になっても雨が止まないようなら野宿だな』
主の指示に、大典太とソハヤは思わず顔を見合わせた。
「それは……大丈夫なのか?」
哨戒任務とはいえ、これは出陣のようなものだ。本来の歴史にはいない異物が長く留まっていいのかと大典太が問えば、大丈夫だろうと主は言う。
『雨宿りくらいなら大丈夫だろうさ。本当は早く帰ってきてもらいたいけど』
遡行軍と戦闘をしなければ検非違使は出現しないし、現時点で遡行軍出現の予兆も無いのなら一日二日滞在したとしてもさして問題はない。そう言った主は、万一戦闘になりそうな気配があったらすぐ連絡すること、と付け加える。
主が言うのであればきっと大丈夫なのだろう。それに、どのみちそれしか方法がないのも事実だ。どんな行動を起こすにしろ雨が止まないと動けないのだ、とりあえず雨が止むまではこの洞窟に滞在するしかない。
二振りが「判った」と機械に向かって頷けば、雨が止んだら連絡をくれと言い残して、主との通信は切れた。洞窟内には、もう雨の音しかしない。
「雨が止むまで、か。とはいっても、止む気配は全然ねえな」
「……そうだな」
ソハヤが洞窟の外を見る。雨は勢いが衰えた様子もなく、ざぁざぁと白く水しぶきを上げて降りしきっている。この雨がどれくらい長く降るのか、大典太には雲の動きを読む知識は無いため分からない。けれどこの様子では、暫くは止みそうにないだろう。
雨が降り始めたのはそろそろ夕暮れに差し掛かるかという時間だったが、もしかしたら一晩中降り続く可能性もある。小降りになったとしても、夜目の利かない太刀が二振り、雨でぬかるんだ夜道を歩くのは危険だ。だからこそ主は野宿の許可を出したのだろうが。
「ま、なるようにしかならねえな。今日は早く帰りたかったんだが」
入口で雨の様子を確認していたソハヤが、状況を受け入れながらもどこか不満げな声を漏らす。洞窟の奥にある岩に腰掛けながら、大典太はなぜだという視線を向けた。
順調に帰城した場合、夕餉の頃になる。もしやソハヤは夜半になにか予定を入れていたのだろうか。今日は久々に夜を二振りで過ごしたいとそう思っていたのだが。
単なる疑問だけではなく、ほんの僅かに悋気が混じった視線を受けて振り向いたソハヤは、大典太にひたりと視線を合わせると口角を上げた。
「せっかく久しぶりに兄弟と時間が合ったんだからな」
その言葉に、僅かな悋気はすぐに消えた。己と過ごしたいからということが分かれば、現金なもので気分は上向く。
「だがまぁ、この雨じゃ帰れそうにないし」
心底残念そうに外を見つめるソハヤに、単純なほどに嬉しくなる。二振りで過ごす、という予定の中に含まれるものを思うと、腹の奥でずっと燻っていた熱にも火がつく。
「……そこは冷えるだろう。暖を取るか」
秋口の、日が沈む時間。洞窟の中は空気が滞留しているせいかほのかに暖かいが、ここから先は冷えていくだけだ。幸いにもジャケットの下の衣類は濡れていなかったため体温を奪われることはないだろうが、長袖の己はともかくとして両肩とも出ているソハヤは身体を冷やしかねない。このままでは任務から無事に帰れたとしても風邪をひく可能性がある。刀剣男士だとて風邪をひくのだ。
大典太の手招きに素直に近づいてきたソハヤの腕を取り、ぐいと引き寄せると、うわ、という驚きの声と共にソハヤの身体が胸に倒れ込んでくる。突然のことにきょとんとしていたソハヤだったが、暫くの後にくつくつと喉を鳴らしてその腕の中に緩く収まった。ぎゅうと己が身体に閉じ込めるように背に腕を回せば、笑いは更に深くなる。
「ちょっとごついが、これも有りといえば有りだな」
「……悪くはないだろう」
「ああ、そうだな。気持ちいい」
意図的に滲ませた霊力が、触れ合った場所から布越しにソハヤに流れていく。霊力不足というほどではないが、足りていない状態だったソハヤの霊力が徐々に満ちていくのがわかった。抱き込んだ身体からゆっくりと力が抜けていく。腕の中から、はは、と気が抜けた楽しそうな声がした。
互いの霊力を分け合い、体温を分け合い、そうして熱が高まっていく。
指先で襟足をすくい、そのまま項へと這わせると、ぴくりと腕の中の身体が跳ねる。お返しにとばかりに肩口にぐりぐりと額が押し付けられ、くすぐったさに小さく笑った。ちょうどいい高さにある髪に顔を埋め、項を撫でていた手を髪に差し入れやわやわと動かせば、くぐもった声が肩口から聞こえてくる。
「……兄弟」
「……なんだ」
「俺たちは任務でここにいるってこと、忘れてないよな?」
霊力と指先に乗せた熱を、ソハヤは違わず受け取ったようだ。戸惑ったような、けれど少し呆れたような声で、任務中だぞ、と大典太を咎める。
受け流されるならそれでいい程度のほんの少しの期待を、任務中だと言うのなら流してしまえば良いものを、ソハヤは拾い上げた。それはソハヤも己と同じ気持ちだと告白するようなものである。
「そうだな。だが、主は任務終了だと言った」
奔放に見えて生真面目なところもあるソハヤのために逃げ道を口にすれば、僅かな間をおいて盛大に溜息をつかれた。
「もし何かあったら、兄弟のせいにするからな」
「ああ。責任はとろう」
「ん。じゃあ、……しようぜ。暖を取るのも兼ねてさ」
「……情緒もなにもない誘いだな」
「だから早く帰りたかったんだよ」
部屋なら情緒だってあったんだがと、身を起こしながら言うソハヤの頬に手を伸ばす。頬をはじめ顔についていた水滴を拭っていると、ふは、と笑い声が漏れた。顔を上げれば、ぽたりとソハヤの髪から水滴が落ちてくる。
「水も滴るいい男、ってやつだな、兄弟」
「お前も」
笑いながら寄せられた顔は少し冷たくて、けれどその中の熱さを知っている身体が期待に震えた。
大典太とソハヤは、閨を共にする仲である。これまでも幾度となく、身体を重ねてきた。ソハヤとそのような仲になったのは、二振りが本丸に揃ってそれほど経っていない頃だったように思う。きっかけは霊力の制御と供給だ。
そこから始まった関係は、思いの外相性がよかったのか長く続いて、初めは触れて抱きしめ合うだけだったのが、今はまぐわいあうことの方が多い。しかし人のように想いを確認したわけではなく、恋仲であるのかと問われれば大典太は首を傾げる。
情はある。好いてもいる。己と同等の霊力を持ち、己と同等に在ってみせるただ一振りの兄弟だ、己にとってはかけがえのない存在であると思っている。けれど、恋慕の情を確認したことはなかった。ソハヤからも特に何も告げられることもなく、聞かれることもなくここまで来ている。
ソハヤはもしかしたらなにか思うところがあるのかもしれないが、彼は何も言わない。何も言わないのであれば、無理に聞くこともない。
情はあれども恋慕の情は不明だ。あるのは三池の霊刀同士という関係だけだ。大典太にはそれで十分だった。
「兄弟、なに考えてるんだ?」
「なんでもない」
いつの間にか座り込んだ己の上に膝立ちでまたがったソハヤに覗き込まれ、股の中心をするりと撫でられる。そのもどかしい感覚でも、腹の奥の熱に火を付けるには事足りた。仕返しとばかりに湿ったタンクトップの中に手を入れると、ソハヤの身体がひくりと反応する。腰をひと撫でした手を滑らせて、胸へと触れる。そこにある突起を指先が掠めれば、小さくも熱をはらむ息が漏れた。
「……今日は反応がいいな」
「……そりゃ、なんたって、久しぶりだからなあ。霊力も、足りてねえし」
声にもねとりとした甘さが乗る。前髪をかき上げられ、視線が合わさる。赤がいつもより、少し溶けて見えた。