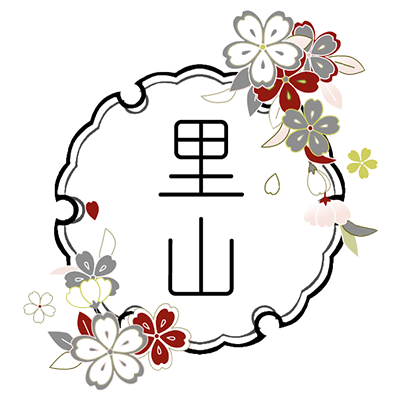このカンケイをなんとよぼう サンプル
SAMPLE
そうして年を越し、大包平も無事に迎えた連隊戦が終わったのが睦月も半ばになる頃。その頃には大典太と大包平の練度上げを主とした部隊が組まれ、出陣を繰り返していた。まずはひと月以内に特に上げること。そのあとはいろいろな組み合わせを試しながら、編成を考えていくことになる。
「おっ、今回は兄弟と同じ部隊だな」
渡された出陣表には己の名が隊長として記載されていた。名を連ねる刀を見るに、検非違使対策で練度が低めのものを中心として、けれど検非違使とも渡り合えるような編成にしたようだ。大典太と大包平の少し前に来た刀ももうすでに練度三十は超えていて、この編成ならばある程度は大丈夫だろうと思う。
「よろしく頼む。……どうせ、戦力にはならないだろうが」
「おいおい兄弟。戦力になるかどうかはここからだぜ。今日は兄弟と大包平の練度上げが主な目的なんだ、二振りには頑張ってもらわないとな。むしろ俺たちがおまけみたいなもんだ」
大典太と大包平は、両者とも元々の能力が高い。練度が低くとも十分に戦えるし、主にも戦力となることを期待されている刀だ。だから一緒に頑張ろうぜとぱしりと背を叩けば、痛みに声を上げることもなくこくりと小さな頷きが返ってきた。
手合わせから数週間、大典太との仲は少しずつ進展していっている。同じ部隊で出陣することも増え、連携も徐々に取れるようになってきた。
そうして何度目かの同じ部隊の出陣先となったのは、江戸時代の戦場、鳥羽。幕末へと向かうその歴史を守るための戦いは、最初の頃こそ胸がざわついたが、今はそれが己の使命であると納得している。
「ここはそんなに強い敵がでるわけじゃない。だからといって、油断はするなよ」
何度か出陣した時代だ、敵の強さは判っている。部隊の平均練度を考えれば滅多なことでは撤退などにはならないだろうが、大包平と大典太は油断をすれば中傷になることだってある。忠告すれば、そんなことは判っている、と大包平が憮然としながら言う。対照的に、大典太はただじっとソハヤを見ていた。
「じゃ、さっさと行って片付けるとしますかね」
記憶と違わず、敵はそこまで警戒するような強さではなかった。幸いにして検非違使が出現することなく、敵の本陣へと進むことができた。
この地には検非違使の出現例がある。目をつけられている時代であるからこそ、練度のばらつきが多少不安ではあったが、ここまでくれば脅威は去ったと言っていい。
「気を引き締めろ!」
敵本陣の陣形を確認し、指示を出す。敵もこちらが侵入してくることが判っていたのか、本陣へ突入すると同時に攻撃が始まった。
ソハヤは敵の部隊長らしき打刀を見つけ、そちらへと向かう。昔は手こずっていたが、練度が四十にもなれば一撃で倒せる敵だ。太刀の中でも早い足を生かし間合いに入り込み、霊力を込めた切っ先を向ける。一瞬動きが止まった隙を見逃すことなく、その銅を横に切りつけた。断末魔すらあげずに、敵打刀が崩れていく。
他の皆はどうかとさっと辺りに視線を巡らせると、すぐ近くで大典太が敵脇差と切り結んでいた。少し押されている。思ったと同時にそちらへ向かう。
「兄弟!」
敵脇差の背後から、蜘蛛のような足を切り落とす。体勢が崩れた脇差を、すかさず大典太が斬りつけた。だが斬られた敵脇差も無抵抗というわけではなく、残った足をばたつかせて最後の抵抗をしてみせる。その一つが、ソハヤの腕にあたった。
「っ……!」
痛みを感じるのと大典太が敵脇差を倒すのはほぼ同時だった。敵脇差は、今度こそ何も残さずに消えていく。
「あー、引っかかれたな」
爪のような部分が剥き出しになっていた肌を引っ掻いたらしく、手の甲から肘の少し手前までざっくりと赤い縦線が走る。傷跡ばかりが大きいだけで思ったよりは痛みもなく、これはさほど時間もかからず直せる傷だろう。刀を納め血を拭っていると、大典太が心配そうにその腕を覗き込んできた。
「……兄弟、すまない」
「あー、いいっていいって。そんなに深くない傷だし、これくらいはよくあることだからな」
実際どの戦場に出ても、大なり小なり怪我は当たり前にある。だからそう珍しくもないから気にするなと笑ってみせるが、大典太は聞こえていないかのように、じぃと真っ赤に走る傷を見ている。肩を落とす姿は図体に似合わず子どものように見えて、思わず笑ってしまう。集まってきた大包平に背中を叩かれて、ちゃんとしろ!と怒鳴られても、その肩は帰城するまで上がることはなかった。
隊長として主への報告をする前に、傷を薬研に見てもらった。綺麗な斬り口だなぁとからかわれながら、傷薬と血止めの軟膏を塗ってもらう。傷口が長いため酷い傷を負ったように見えるが、それほどの痛みはない。後でちゃんと手入れをしてもらえとの言葉を背に部屋をでると、眼の前にのっぺりとした壁があった。
「うわっ」
「兄弟」
驚いて声を上げたソハヤだったが、降ってきた声に顔を上げれば、大典太の顔がそこにあった。
「何だ兄弟か、驚かすなって。びっくりしただろ」
「……すまない、驚かすつもりはなかった」
「判ってるって。でもどうしたんだ、こんなところで」
薬研の部屋に用でもあったのか、と野暮なことを聞くつもりはない。大典太がここにいる理由は何となく察しているが、敢えてそう尋ねてみた。大典太が何かを言おうとした瞬間に、薬研がひょこりと顔を出す。
「なんだ、あんたも兄弟が心配なんだなぁ」
からかうような声に、大典太はもごもごと口を閉ざしてしまう。それすらからからと笑う薬研を、肩越しに振り返った。
「お前なぁ」
「お? なんか邪魔しちまったのなら悪いなぁ。さぁ旦那方、あとは自室でやってくれや」
薬研に追い出され、二人揃って自室へと向かう。歩いている最中、大典太は心配げな雰囲気を出す割には、何も言ってこなかった。そんなに引きずるもんでもないんだが、と思ったが口には出さないでおく。
「そんなに心配するなって。もう痛みも出血も治まった。さっきも言ったが戦場じゃあこの程度の傷ならよくあるし、もっと酷い傷を追うことだってあるんだ。兄弟が気にすることじゃないさ」
「だが、それは俺が脇差を仕留め残ったからできた傷だろう」
「兄弟のせいじゃなくて、悪あがきをしてきた敵のせいだな。敵があんなふうに悪あがきをしてくるのは予想外だった。それに、あんな近くに突っ立ってた俺も悪いな」
だから、どちらが悪いというものではない。そう言っても、大典太は納得がいかないようだった。こんなにも心配症だったのだろうか、己の兄弟は。
「そこまで兄弟が気にするっていうのなら、次の戦では誉れを取ってくれ」
眉間にしわが寄った。眉をひそめているだろう顔を見上げて、ソハヤは告げる。
「戦働きでの失敗は戦働きで取り返す。そうだろう?」
反論を許さぬように、困惑が浮かぶ赤い目をじっと見つめる。暫くそうしていると根負けしたかのように、判った、と大典太が小さく呟いた。
「よし、じゃあさっさと着替えてこようぜ」
己も大典太も帰城したときのまま、戦装束姿だ。がちゃがちゃとした武具は、室内で着用するには向いていない。
「……手伝おう」
「これくらい一人でできるさ。じゃあまた後でな」
物言いたげな大典太を置いてソハヤは自室へと入り、戸を閉めた。大典太の気配は少しの間そこにあったが、やがて隣の部屋へと気配が移動した。
ふぅ、と息を吐く。責任を感じるのはいいが、そこまで気にしなくてもいいだろうに。
「でもま、次は気をつけるとするか」
自分のせいで誰かが傷つくことを嫌う性格なのだろうと独りごちて、ソハヤは武具の紐に手をかけた。
それからだ、大典太がソハヤを妙に気にかけるようになったのは。
風呂や内番のとき、手伝おう、と声をかけられる。それだけならばまだいいが、手伝いがいるのはそっちの方じゃないのか、という時にも、こちらを気にする素振りをする。
ソハヤが怪我をしていたときならば、傷を負わせた負い目からの行動だろうと判るのだが、怪我が治っても、練度が上がっていっても、大典太は気がつけばソハヤの側にいるようになった。
今もそうだ。気遣わしげな、それでいて頃合いを見計らっているような視線がソハヤに突き刺さっている。
「兄弟」
きたなと、大典太が声をかけてくる頃合いすら判るようになったソハヤは、平静を装って大典太を振り返る。
「何だ兄弟」
「俺が持とう」
大典太が見ているのは、ソハヤが抱える資源だ。今は遠征任務中で、そこで得た資源を本丸へ持ち帰っている最中である。大典太はすでに玉鋼と砥石を他の刀よりも多めに引き受けていて、両手が塞がっている。ソハヤが持つのは玉鋼で、けれど大典太よりは明らかに抱える量は少ない。だというのに、大典太はそれを預かろうというのだ。
「ありがたい申し出だが、これくらい俺でもちゃんと持って帰れるさ」
「だが、お前は昨日出陣だっただろう」
「ああ、疲れてるんじゃないかって? 大丈夫だって、これでも一応太刀だからな。でも、気遣いはありがたく受け取っておく」
ひらひらと言葉を躱していけば、元々明るく交流の得意なソハヤに他のものとの交流が苦手な大典太が敵うわけもなく、やがて大典太は押し黙る。
「それに、兄弟だって昨日も遠征だったんだろ? 疲れはお互い様ってわけだ。帰ったらひとっ風呂浴びて、おやつでも食べてゆっくりしようぜ」
「……ああ」
それ以上、大典太は何を言ってくることもない。ただ時折、ちらりと視線がよこされる程度だ。その視線に気付かれないように、気合を入れて資源を持ち直した。
疲れているか、といえば疲れている。昨日は久々に検非違使の連戦で、まだ練度も上がりきっていない仲間を抱えたままでは、練度が一番上のソハヤが頑張るしかなかった。他の刀よりも多く敵を打ち取り、誉れをもらったことである程度の疲労は抜けたが、それでも疲れるものは疲れる。一晩寝て、内番働きができるくらいには体力も気力も回復したが、遠征となるとまた違う。いろいろな事情が重なって昨日の今日で遠征に行くことになった。遠征に行ってもいいと、酷く申し訳無さそうに頼んできた主に告げたのは自分だし、これくらいの疲れならばなんとかなる。
もう一度資源を抱え直したソハヤに、大典太の視線が刺さる。疲れているのなら、と雄弁に語るその目に、困ったように笑う。
「兄弟はこの間からそればっかりだな。どうしたんだ」
尋ねてみても、大典太は何も答えない。もう何回も繰り返したやり取りだ。だから正直意味がないとは判ってはいるが、それでも大典太の真意が判らないこの状況に、つい尋ねてしまう。
「なにか心配事とか、困ってることとかあるのか? おかしな夢を見たとか。だったら相談にのるぜ?」
最も、そういった雰囲気ではないことは知っているが。無表情に見える大典太も、感情がよく顔に出る主に似たのか、じっと見ていれば感情に合わせて表情が変わる。今言ったことの中でなにか心当たりがあれば表情を変えるだろうと思ったのだが、一つも変わらないところを見るとどれも外れらしい。いつの間にか足を止めて、ただじっと見つめ合うだけになってしまった。
「……おい、そこの三池兄弟。置いていくぞ」
今回の遠征の隊長である山姥切から声がかかる。山姥切は元より置いていくつもりだったのか、二振りが歩き出す前にさっさと行ってしまう。それを追いかけようとしたソハヤの背を、ぽつりと漏れた声が追う。
「……お前は、俺を頼ってはくれないな」
「え」
思わず立ち止まって振り向くが、大典太は呟いたことすらなかったかのように、ソハヤの隣を通り抜けていく。
「兄弟?」
問いかけても、大典太が振り返ることはなかった。