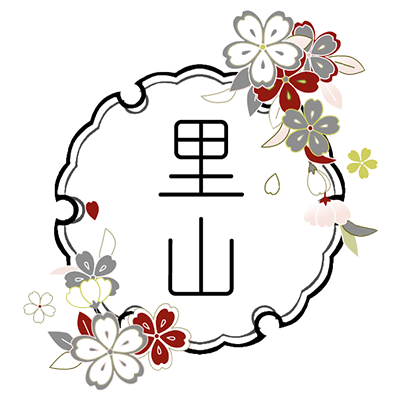赤に微睡み、 青に行く サンプル
SAMPLE
私はそこにいますか
本丸解体の報せを受けたその日は、ざわつく内心とは真逆に青く晴れ渡っていた。
陸奥守は、倒れてから二日後には無事に床上げをし内番に復帰した。主の判断で出陣は禁止されたが、それ以外のことは普段どおりにできるようになった。あれ以降体調が悪化することもなく、普通に過ごしている。己が倒れたのはたまたま主の体調不良が悪化したからで、特に何かあったわけでもない。これまでと同じように内番と出陣を繰り返して過ごしていくのだろう、と思いはじめた頃。
「すまん」
主が頭を下げてきた時、陸奥守はどうすることもできなかった。
「主のせいじゃあないろう」
そう言うのが精一杯だった。
「俺のせいだろう」
「主」
明るい日差しが差し込む部屋の中だと言うのに、空気が重い。
「……俺の病気のせいで、本丸が解体されるんだ」
どこかから誰かの笑い声が届き、沈黙したままの部屋に反響する。笑い声はひどく遠く、現実味がない。
陸奥守が倒れた時、主は政府に赴いて自身の体調不良についての診察を受けていた。何故陸奥守が倒れたのかを調べるためでもあったが、同時にしばらく続いていた体調不良について診断してもらうためでもあった。突然刀が倒れ、数日意識不明となった事例は年間数十件は発生するらしい。審神者の体調不良及び霊力の不安定からくる揺らぎが原因になることも多いようで、本丸の調査をしながら主の状態についても診察が必要だと判断されたようだ。
そうして陸奥守が倒れてから一週間と少し経った頃、ようやく結果が届いた。通常の診断結果ならば電子で届くはずだが、こんのすけが一枚の書状を持ってやってきた。政府の印が押され、本人でなければ開かない術式で厳重に封された書状に書かれていたのは、主の体調不良の原因である病の名と、本丸解体の報せだった。
反転病。初めて聞く病名だった。現代の病に詳しいわけではないが、一般的な病名ではないだろうことは、その下に長々と書かれた病状と対応についてを読めば分かる。
反転病とは審神者だけが罹る病気であり、神気の性質が反転し制御不能状態となり、審神者及び刀剣男士、そして本丸にとって毒になる病気だという。この病気に侵されたものは力の制御ができなくなるため、本丸から出ることが許されない。審神者から審神者に伝染る事例は確認されていないが、どんな悪影響があるか分からないからだ。
「……主」
この病気は治療法が確立されてない。震える声で主が告げる。それは、冷えた心を更に冷たくする。治療法はなく、ただ病が進むのを待つしか無い。そして、最終的には病は発病者の体を蝕み、命を奪う。
治す手段もなく、隔離しようとも対処法はない。そんな中で政府が取った方法は、発病者と発病者の本丸を隔離すること。
非情だ、と政府を詰ることはできる。だが、戦争中で余裕がないからこその処置だ、と頭の片隅で納得もする。政府の手のものによる発病者の殺害でないだけ、まだ人的と言えるのかもしれない。発病者を政府から隔離するのは、間接的な殺害と変わりはないが。
それは主も分かっているのだろうが、感情としては受け入れられないはずだ。感情を抑えて淡々と話しながらも、その手は膝上で強く握り込まれている。
「……主はどうするがよ」
「……審神者になるときに、死ぬことについては覚悟はしている。政府がこういう手段しか無い、って言うならそれに従うまでだ」
「それでえいがか?」
政府に直訴したり、対処法を探して足掻くこともできるだろう。けれど主は、政府の決定を受け入れるらしい。
「薄々、自分の状態がおかしいことには気がついていた。……最近よく鍛刀失敗するし、普通に過ごしているのに力が抜けていく感覚もある。じわじわ削り取られていくような感じだった」
だから政府からの通知に納得もした、という主は、もう自身の境遇をどうにもならないものとして認識しているらしかった。諦めの早さと状況を受け入れる早さは主の長所でもあったが、こういうときには悪い方に作用する。
「足掻いても無駄だということは、自分が一番分かってる。……政府は本丸を出るなって言ってるけど、違う。出れないんだ、俺は。昨日、万屋に行こうとして本丸の結界に拒まれた」
「それは……」
そういえば昨日、万屋に出かけると行って出ていった主が、少し調子が悪いからと直ぐに戻ってきたことがあった。代わりに鯰尾が骨喰を連れて万屋へ行ったが、そんな理由だったのか。
「多分、もう駄目なんだろうな。だから、」
「分かったぜよ。おんしが決めたことじゃ。わしもおんしに付き合おうちゃる」
弾かれたように顔を上げた主は、ひどい顔をしていた。
「陸奥守」
初期刀は審神者の刀だ。他の刀達と違い、主と深く結びついている。体調不良の影響が一番に出るほどに。
初期刀は正しく審神者の刀である、というのは、顕現した当時にこんのすけから聞かされている。「正しく」が何を指すのか、陸奥守は始めから理解している。
「おんしが死ぬまで、初期刀として付き合うぜよ」
「……残れば、多分錆びて朽ちるぞ」
反転病とはそういう病気であるらしい。反転し毒となった神気が本丸を朽ちさせ、刀を錆びさせる。刀剣破壊でもなく物として錆びることは刀にとっては辛いことだろう、と主は案じているようだ。自分の身よりも物の方を案じるその心は好ましいが、人と物は違うのだ。まずは自分の心配をしてほしい。
「物はいつか壊れるもんじゃ。なんちゃあないき、心配はいらんぜよ。それに、話し相手が必要じゃろ?」
初期刀だから最期まで共をするという気持ちが強いのはあるが、それでなくとも、己だって主のことが大切なのだ。
だから主と一緒に本丸に残ると再度告げれば、主がくしゃりと顔を歪ませる。主の泣きそうな表情など、最初の出陣のときに重傷を負って帰ってきた時以来だ。あれから強くなると互いに誓ってここまで来た。まだ一年も経っていないあの頃を懐かしく思う。
「解体時期はいつじゃ」
「……一週間後」
「……たまぁ」
思ったよりも早い。それだけこの病気の進行が早いのだろう。診断書によれば、主の症状は中期だったようで、だとすれば今はそれよりも進行しているはずだ。己の体には今の所不調は現れていないが、主はあれからも時々辛そうなときがあったので、確実に進行しているだろう。
「……すまん、お前に苦労を強いる」
主の肩が小さく震えている。その肩にぽんと手をおいて、心配させないように笑った。
政府への了承の返信と解体までの予定調整は、主の精神的負荷を考慮して明日以降行うことになった。考える時間も必要だから一人にしておこうと執務室を座し、行くあてもなく本丸内を歩き回る。
広間では脇差が頭を寄せて何か話し合っていて、外では短刀たちが遊び回っている。厨に顔を出せば今日の台所当番が支度をしている最中で、特別に味見をさせてもらった。道場では手合わせの内番以外のものも鍛錬にきており、隅では何事か話し合っているものもいた。
出陣している部隊が一部隊、遠征に行っている部隊が二部隊。もう一部隊もいるが、主の体調不良の件もあるので、最近は三部隊で回している。
いつもどおりの本丸だ。主と己が始めて、ここまで刀が増えた。賑やかで居心地の良い、己の居場所。この本丸があとひと月で解体となる。そう思えば胸が締め付けられるような寂しさが湧き上がり、どうにもじっとしていられなくて本丸中を隅々まで歩き回った。
主と同じように己も思っていたより動揺しているらしい、と自嘲気味な笑みが漏れる。初期刀として皆が安心していられるように堂々としておきたかったが、今は少し無理そうだ。
自室で暫く頭を冷やそうと目的地を定め、遡行用の門を通りがかったとき、ちょうど出陣をしていた第一部隊が帰ってきた。今日の出陣は以前も出陣したことのある場所で、今の戦力であれば攻略はさほど難しくない場所だ。戦場での権限は隊長に全て任せていて、だから先程主と政府からの書状を読むことができていた。
「おう、陸奥」
隊長であった和泉守が、陸奥守の姿を見つけて手を挙げる。出迎えご苦労とでも言いそうな表情に笑って、普段のようにお帰りと迎え入れた。
「どうじゃった?」
「楽勝だったな。ま、俺が隊長な時点で勝ちは決まったもんだろ」
「はは、言うのぉ!」
怪我をしているものもおらず、部隊はそこで解散となり、皆散り散りに本丸へと戻っていく。和泉守も主へ報告をすると言って執務室へ向かおうとするが、思わずそれを引き止めた。まだ主は考え込んでいるかもしれない。今はまだそっとしておきたいと、体調が少し優れないからと言い訳をして己が代わりに報告を受けると言えば、和泉守は疑いもせずそうかと頷いて報告をしてくれた。
「ほいたら、後でわしがしっかと伝えておく。引き止めてすまんかった」
報告は全て終わっただろうに、なぜか和泉守はその場から動かなかった。他になにか主に伝えたいことでもあるのだろうかと見上げると、こちらを見つめてくる水色の目と視線が合った。
「ん? どういた和泉」
「……お前、なんかあったか?」
「……おん?」
一瞬どきりとするが、すぐにその動揺を奥へと隠して何がだと問う。じぃと見つめる目が、訝しげに細められる。
「なんか、隠し事してねえか?」
なぜ分かるのだろうか。驚いて、言葉に詰まった。最近、この刀は妙に鋭いときがある。
「隠し事はしちょらんぜよ」
「……ふーん?」
顔を背ければ肯定と取られてしまうので、探るような視線から目を逸らさないでいると、暫く見つめ合ったのち和泉守から視線を外す。
「まぁいいけどよ、体調悪くなったらすぐ休めよ」
「……なんじゃあ、わしの体調を心配しゆうがか」
己が完治したことは全員が知っていることだったので、まさか体調の心配をされているとは思ってもいなかった。
「主が体調が悪いんだろ。だったら気づかないうちにお前にも影響出てるかもしれねえだろうが」
ばつの悪い顔をして顔を背ける。髪から覗いた耳が少し赤い。
「……優しいのぉ」
ぽつりと呟いた声は聞こえなかったらしく、なんだよ、と照れを隠そうとして失敗したような不機嫌そうな声が落ちてきた。
「いんや、おんしはなかなか心配性じゃと思っただけじゃ」
「お前が大人しくしてりゃ余計な心配はいらねえんだよ」
「おお、ほいたらやっぱり、心配してくれゆうか!」
ぐ、と和泉守が言葉に詰まったのに笑いながら、その気遣いがひどく嬉しいと思う。たったそれだけのことで、気分が軽くなる。本丸が解体されるという衝撃や不安が完全に和らぐわけではないが、じわじわと胸に広がっていく温かさに少し冷静になれた。
そうして思う。己が不安がっていては、皆に、そして和泉守にまたいらぬ心配をかけさせてしまう。主にもまたあの顔をさせてしまうだろう。ならば最期まで初期刀として近侍として、しっかりしていなければならない。
未だもごもごと何事か言い訳を呟いている和泉守を見て、決意をするように笑った。