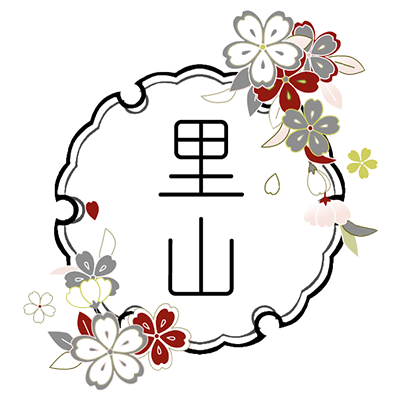朝霧において迷路-まよいみち- サンプル
SAMPLE
熱が落ち着けば、次にするのは後始末だ。本丸のように後始末に便利なものはなく、未だ止まぬ雨に手ぬぐいを濡らし、身体を清めた。ざっと自身の身を清めてから、大典太はソハヤの身体を濡らした手ぬぐいで拭き始める。無心で後孔から精をかき出し、太ももを伝うそれを拭いとっていく。
岩にしがみつかせていたソハヤは多少手や腕を赤くしながらも、敷いていた服のおかげか怪我はないようだった。
「……もうちょっと緩やかでも、良かったんだが」
「……あまりない状況だったからな……」
「ふぅん? 興奮したってか」
これでも耐えた方だ、とは言わないほうがいいだろう。なんとなくバツの悪い気持ちになり、無言で作業を進める。ソハヤは笑っていたが、中から精を掻き出す動きにぴくりと身体を跳ねさせて、口を閉ざす。二振り共が口を閉じてしまえば、あとはただ激しい雨音が洞窟に反響するだけだ。
「……寒くはないか」
「さっき暖を取ったからな、むしろ暑いくらいだ」
確かに、風が吹かない洞窟内は、最初にこの場所に来たときよりは少し蒸し暑く感じる。湿気のせいか、どこか空気も重い。
己が吐き出した精を拭い取った手ぬぐいを雨で濯いで固く絞り、その間に着替え終わったソハヤの肌に薄らと浮かんだ汗を拭ってやる。くすぐったい、とソハヤが笑って身を捩るのを押さえて、顔、首、腕を順に拭いていく。肩に差し掛かった時、そういや、とソハヤが声を上げた。
「さっき噛んだだろ、肩」
それは嗜めるような響きでもあり、呆れたような声音でもあった。タンクトップから覗く肩には、薄らと赤い噛み跡が残っている。何を思ってそこを噛んだのか、ソハヤが気づかないはずがない。
「心配性だな、兄弟は」
ぐしゃぐしゃと髪の毛をかき混ぜられる。直ってるって、と言いながらソハヤは証明して見せるようにぐるぐると肩を回した。綺麗にふさがったそこは、傷を負ったことを知っていなければ何もないように見える。
「どうしたよ、兄弟。戦で怪我を負うことなんか今までだってあったじゃねえか。まぁ中傷を負ったのは久々だったけど」
戦いの仕方を忘れてたつもりはないが、ちょっとひやっとしたな。ソハヤの言葉を聞きながら思い出すのは、見舞いを終え手入れ部屋を出た後のことだ。
ソハヤと同じ部隊で出陣していた桑名江に呼び止められた。足を止めた大典太に、桑名はソハヤが怪我をした時の状況を話してくれた。篭手切江を庇って肩に槍を受けたというのは、ソハヤが怪我をしたと伝えに来てくれた今日の近侍から聞いていた状況とほぼ同じだったが、違ったのはその時のソハヤの動きだった。
『初めから、盾になりに行っているようだった』
篭手切に襲いかかる敵槍に気がついた時、誰が走っても敵を倒すには間に合わない状態だったらしい。それは一番近くにいたソハヤもそうだった。だがソハヤは躊躇なくその身を篭手切の前に身を踊らせ、盾になったという。
それだけを聞けば特におかしなところはないように思う。仲間をかばうために前に出るのはよく聞く話だ。己も以前に身を挺して仲間を守ったこともある。
だが桑名はそこに危うさを見たらしい。自己犠牲のような、躊躇なく自分をなげうつような。なにがどうとは言葉に出来ないんだけど、と申し訳無さそうにしながら伝えてくれた桑名の言葉の端々には心配が滲んでいる。
そういえばこの刀は徳川由縁の刀であったかと思い至り、けれど己に器用な返しはできないので、分かった、気をつけておこう、と言うのが精々だった。それでも、桑名は少しほっとしたようだった。
その後様子を見に来た部隊長だった長谷部にも、「守るならば己もしっかりと守れと、お前からも言っておいてくれ」と言われたので、桑名が感じた危うさを長谷部も気づいていたようだ。
思い返しながら、この刀はそんな戦い方をしていただろうか、と綺麗になった肩に手を伸ばす。確かに多少、己が傷つくのを厭わないところはあったが、危惧するほど無鉄砲ではなかったはずだ。
「なんだよ兄弟」
「……長谷部が怒っていたぞ」
「ああ、昨日も散々怒られた。兄弟にも言うのは卑怯じゃねえか、長谷部」
つるりとした皮膚を撫でれば、くすぐったそうにソハヤが笑った。
「まぁ、久々に中傷になったから気になるのも分かるが、折れちゃいないんだ。そろそろ切り替えていこうぜ」
「……そうだな」
己は、桑名や長谷部が言うソハヤの戦い方を見ていない。そんな己が何かを言うことは出来ないし、言ったとしてもソハヤには響かないだろう。ならばソハヤの言う通り、少し気になる点はあるにせよ、この件はそろそろ区切りをつけた方がいい。
「だが、中傷になれば心配はする」
「それもそうか。心配かけてすまなかった、兄弟」
わしゃりと髪の毛をかき混ぜられる。それだけで心が軽くなるのだから、本当に現金だと思いながら大典太は立ち上がる。
「雨、止みそうにねえな」
雨は相変わらず激しく降り続き、ざぁざぁと洞窟内に音を反響させている。もうすでに外は暗くなり始め、すぐに夜になるだろう。今はまだ洞窟内も温かいが、夜になれば冷えていく。火をおこす道具があればよかったが、哨戒任務のためあいにくとそのようなものはなかった。寄り添って眠るしかないか。
使い終わった手ぬぐいをその雨で洗い、水を切る。これらも帰城するまでに乾けばいいが、風もなく湿気が籠もる洞窟内では難しいかもしれない。
そんなことを思いながら振り向いて、そうしてそこに広がっていた光景に眉根を寄せる。
洞窟の奥にある岩に腰掛けているソハヤのその向こう、洞窟の一番奥が、真黒に染まっていた。まるで光さえ通さないような暗闇が、いつの間にかぽつんと広がっている。
そして何故か目を見開いているソハヤの後ろに、何かがいた。
顔が潰れ、首が横に直角に折れ曲がった、人のようなもの。ほんの僅かの肉と皮で辛うじてつながっている首からは、血がぼたぼたと落ちている。
気配がないので少し驚いたが、この辺りをさまよう浮遊霊だろう。この地は天下分け目の大いくさがあった場所だ。昼間に任務をこなしているときもこの類の霊はよく見かけた。低級霊ならばと僅かに霊力を放出しようとした瞬間、それがソハヤに向かってゆらりと動いた。
「兄弟!」
叫んだのは、ソハヤだった。
後ろ、と言われて弾かれたように振り返った大典太が見たのは、潰れた顔にぽかりと空いた闇だった。後少しでも動けば触れてしまいそうなほど近くに霊がいた。気が付かなかった、と今更ながらに背がぞわりと粟立つ。
大きく見開かれた目の中は空洞で、洞窟奥と同じくらい真暗な闇を湛えたそこからは、赤いものが流れ出ている。普通の人間ではありえない、胸ほどまで大きく開かれた口は、どこまでも真赤で。
食われる、と思ったと同時、身体に衝撃が走る。ソハヤに突き飛ばされたのだと認識したのは、己の立っていた位置でソハヤが二体の霊に挟まれて取り込まれるのを見たときだった。