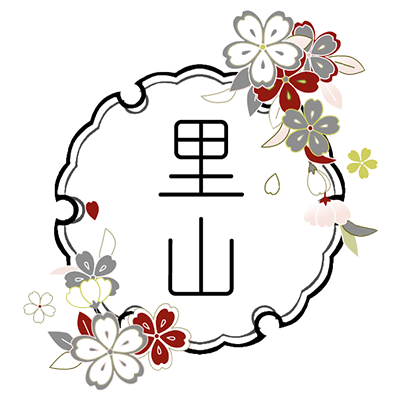満たして、もっと サンプル
SAMPLE
双方向性の限りない熱
睡眠姦
本文全て掲載
すう、と近くで聞こえる小さな呼吸音を聞きながら、大典太光世は閉じていた目を開けた。広がる闇の中で幾度か目を瞬き、じぃと闇を見つめていればおぼろげに天井の形が見えてくる。隣を向くと、同室の刀が大典太と同じように仰向けで布団に横になっているのが見えた。
「……兄弟」
呼びかけてみるが反応はなく、小さな寝息が聞こえるのを確認して、音を立てないようにゆっくりと上体を起こし枕元にある照明をつけた。部屋全体を明るくするほどではない照明は、けれどしっかりと隣に眠るソハヤノツルキの寝顔を照らし出す。
大典太は久しぶりに見るその寝顔を暫く見つめていたが、ソハヤはその視線にも気づかず静かに眠っている。手を伸ばし頬に触れると、少しだけソハヤが身じろいだ。んん、と喉を鳴らすような声を出し、触れる手の感覚から逃れようと、僅かに顔を背けた。
「……ソハヤ」
寝ていると確信はしているが、念の為に声をかけてみる。起こしてしまったならば、この後は何もできない。
呼びかけに応えはない。頬をゆっくりと撫でても、前髪を上げてみても、今度は身じろぎする様子はなかった。まだ眠りの中にいるようだと安堵して、大典太は空いている手でソハヤの手に触れる。ぴくりと指が動くが、ただの反射に近い。
ソハヤはぐっすりと眠っている。眠りが浅いソハヤがよく寝れると言う寝酒をして就寝しているのだから、いつもよりも眠りは深いだろう。
更に眠りを深くするために、軽く握り込んだ手から、慎重に薄くゆっくりと霊力を流し込んで馴染ませていく。流し込まれる霊力にぴくりとソハヤの瞼が震えるが、無意識下でもソハヤは大典太の霊力を受けて入れているようで、流し続けるうちに震えは止まり呼吸も深くなっていった。己が霊力がソハヤの体を薄く包み込んだのを感じて、集中するために閉じていた目を開ける。
ほのかに照らされたソハヤの呼吸は、先程よりも深くなっている。頬を撫でても、首筋に触れても、かえる反応はない。
準備が整ったと、小さく安堵の息を吐く。
今日は足だ。
逸る気持ちを抑えて、大典太はソハヤの体にかかる布団をめくった。
頬、耳、首、鎖骨、胸。自身の布団に座ったまま横から手を滑らせ、肌の温もりと感触を楽しむ。起こさないように慎重に、大典太は眠るソハヤの体に触れていく。
支給の寝間着の合わせから滑り込ませた手は、すぐに目的のものを見つけた。張りのある胸を何度かやわやわと揉んで、感触を楽しむ。中心の突起へと触れて指先でそこを転がして遊んでいると、柔らかだった突起が硬くなtた。力加減を間違わないように注意しながら指の腹で緩く摘んでこりこりと擦れば、より存在を主張しはじめる。もう片方も、と襟に手をかける。寝間着の帯は既に緩めてあったので、少しの力で簡単に胸がさらけ出された。
片方の胸も同じように触っていると、ふ、と吐息が聞こた。己の息ではないそれに顔を上げると、ソハヤの顔が、明かりに照らされただけではない赤にほんの少し染まっていることが確認できた。硬くなった胸の先を両方同時につまめばぴくりと体が震えて、小さく開けられた口から再び僅かに熱を帯びた息が漏れた。けれど、ソハヤの閉じられた目が開くことはない。
胸を弄る手に合わせて身体が震え、時折息が漏れる。己が与えた刺激を受け取ってくれていることに嬉しくなって、胸が温かくなると同時に腹の奥が熱くなった。
弄った胸は手を離してもぷくりと主張したままで、照明が作り出した影が胸に落ちている。それに満足して、脇腹をなぞりながら手を下げていく。盛り上がる筋肉の形をなぞるように腹に触れるとくすぐったかったのか身を捩ったが、手を止めるとすぐに動かなくなる。
帯はそのままに足を割り開くと、その間に移動して振動を与えないように腰をおろす。今日の目的である足の付け根に触れるために下着に手をかけ、太ももの半分くらいまでずらしたところで一度顔を上げてソハヤを見た。
ソハヤの顔を見ながら露わになった付け根にそっと指を這わす。そこに触れたのは初めてのことだ。
ん、と声が上がる。ソハヤにとっても初めての感覚であったので違和感でも感じたのだろう。初めての場所に触れると、だいたい小さく反応が返ってくる。起きたことは一度もないが、それでもいつその目が開くかは分からない。
起きてしまえば、きっと受け入れてはくれないだろう。だから大典太は慎重に、慎重に、起きないように、今日もソハヤへ触れる。
大典太が寝ているソハヤに触れ始めてから、ふた月ほどが経っていた。
その日、大典太は非番を持て余して部屋で読書をしていた。
まだ顕現して数ヶ月しか経っていなかったその日の非番をどう過ごしていいか分からず、手持ち無沙汰の状態だった。同室であり顕現してから世話を焼いてくれていたソハヤも昨日から日をまたぐ遠征に出て不在だ。他の顔見知りの刀と話したり茶を飲んだり囲碁などをして過ごすこともあるが、あいにくと皆、出陣や用事などで本丸にいなかった。
蔵に籠もることを禁止され、畑の手伝いや馬当番の手伝いも憚られ、かといってあまり当番を担当したことのない料理当番の手伝いもでない。昨日出陣から帰ってきてから少し腹の奥がもやもやしていたので、暇なものがいれば手合わせでもしてもらうかと道場へ向かうが、同じく非番のものが思ったよりも多数いたため諦めた。
もやもやを抱えながらどうしようかと歩いていると、初期刀が読書でもして時間を潰せばいい、と教えてくれた。そこで初めて、この本丸には図書室があると知った。
図書室には歴史書や歴史文学、刀剣男士が学ぶための人間学から、小説、漫画、絵本などの娯楽本が多数あり、その中から人間学の本と歴史書を借りて自室に戻り、読み進めていた。
興味深い、というわけではなかったが、それでもじっとしてひとつの物事に集中するのは性に合っていたらしい。
「ただいま」
突然聞こえてきた声にはっとして顔を上げれば、疲れた顔をしたソハヤが入ってくるところだった。遠征部隊が帰城するのは夕方の筈だが、と不思議に思ったが、外を見ればもう夕日に赤く染まっていて、今がその夕方だと知る。それほどまでに集中していたらしい。
「すまねえ兄弟、少し借りる」
がちゃがちゃと乱雑に防具を脱ぎ捨てて内番服に着替えたソハヤが、言うやいなや大典太の背中によりかかってきた。そのまま少しだけ下に下がっていき、もぞもぞと身体を動かして位置調整をした後、一つ大きな息を吐く。その音が聞こえたと同時に、背中に更に重みが加わった。
「疲れたか」
「んー……」
「……もうじきに夕飯だぞ」
「おう」
生返事を返すソハヤに、珍しいと思う。顕現してからずっとソハヤと過ごしてきたが、ここまで疲れた姿を見せることはあまりない。遠征先でなにかあったのだろうかと背後に意識を向けても、ソハヤは反応しない。
「兄弟?」
呼びかけても応えがなかった。己が呼びかければ大体は声を返してくれるというのに。怪我でもしていたら危ないとソハヤの気配に意識を集中すると、予想に反して非常に穏やかな霊力の流れがあった。
やがて、すぅすぅと小さな寝息も聞こえてくる。どうやら、疲れて眠ってしまったらしかった。これまた珍しいことである。他刃が昼寝をしているのは見たことがあったが、ソハヤが昼寝をしている姿は一度も見たことがなかった。
そうして意識していれば己の霊力がソハヤへ流れていくのが分かる。借りる、というのは背中のことでもあり、霊力のことでもあるのだろう。霊力が不足するくらい疲れたのか、霊力が不足するような自体があったから疲れたのか。起きたら聞いてみるかと、意識を目の前へと戻す。
どうしようかとしばし考えて、再度本を読むことにした。読書を再開して少しの間は背中に感じるソハヤの重みと体温が気になったが、それもすぐに気にならなくなるほど集中する。
次に大典太が本から顔を上げたのは、背中でソハヤがもぞりと動いたからだった。すっと寝起きの気配から通常の気配へと戻ったソハヤに大典太が兄弟と声を掛けるよりも早く、違う声が部屋に響く。
「ソハヤさん夕飯……ってあれ、大典太さんも居たんですね、ちょうどよかった。夕飯できたそうですよ」
ひょこりと顔を出したのは鯰尾藤四郎だ。鯰尾は皆から遠巻きにされがちな大典太にも隔てなく話しかけてくる刀で、今日も一つ立った髪の毛を揺らしながらにこやかに話しかけてくる。
「おお、わざわざわりぃな」
応えたのはソハヤだ。先程まで寝ていたことを微塵も声に出さず、立ち上がって着ていなかったらしい内番服の上着を羽織っている。
「そういえばソハヤさん、遠征から帰ってきておやつ貰ってませんでしたよね? 歌仙さんが残してあるから声かけてほしいって」
「あー、了解。疲れてたからそのままこっち来たんだよな。鯰尾は食べたのか?」
「はい! 美味しかったですよー!」
「期待大だな。ほら兄弟、行こうぜ」
弾む会話を見ているだけだった大典太にソハヤが振り向き、漸く大典太も腰を上げた。どうやら鯰尾が呼びに来たのは大典太たちが最後のようで、三振りで食事が用意されている広間へと向かう。
広間へ向かう途中、ソハヤは合流した後藤藤四郎と共に先に進んで行った。腹が減りすぎている、という会話が少し遠くから聞こえる。
「ソハヤさん、もしかして寝てました?」
ソハヤたちの会話がはっきりと聞こえないくらいまで来てから、鯰尾がぽつりと問う。思わず見下ろした先で、またぴょこりと髪の毛が揺れた。
前を歩くソハヤは常の状態と変わらず、鯰尾が来る前にはもう起きていた。ソハヤが寝ていたところ目撃していないのに察することが出来たのは、脇差の偵察力というやつか、と目を瞠っていると、違いますよと笑われる。
「遠征先で眠れてなかったみたいなんで。帰ってきたときもお八つも食べないしお風呂にもいかずに直ぐに部屋に戻っちゃうし、ちょっと心配だったんですよね」
「眠れていなかった?」
そういえば鯰尾はソハヤと同じ遠征部隊だったことを思い出す。
「たまにいるんですよ、遠征で眠れない刀。気を張っていたっていうのもあると思いますけど。日をまたぐ遠征や出陣ってなかなかないですし。ソハヤさん元々眠りが浅いほうだったから、他のものの気配があると眠れないんだと思うんですよね。何回か一緒に遠征に出てますけど、交代で寝ててもすぐ起きちゃってたから」
それこそおかしな話だと目を瞬かせる。ソハヤの眠りが浅いなど、初耳だった。
「……兄弟は、普通に夜寝ているが」
大典太は顕現してからずっとソハヤと同室だ。先に顕現していたソハヤの部屋に大典太が入った形だが、それでも数ヶ月一緒に居て眠りが浅いのに気づかないことはない筈である。よほどソハヤがうまく隠していれば別だが、もし隠していたとしても霊力に乱れが生じるので、それもないだろう。
「大典太さんだからですね! 俺にも覚えがあります。やっぱり知ってる刀や身内の刀がいるところだと落ち着くんですよね」
「……そういうものか」
「そういうものです」
まぁ眠れてるのなら良かった、と己が顕現する前のソハヤを知っているらしい脇差はうんうんと頷く。俺達も早く行きましょと大典太を促し少しだけ歩調が早くなった鯰尾の後を追いながら、大典太は先程のソハヤの行動を思い出していた。
遠征で眠れていなかったソハヤが真っ先に部屋に戻り、己の背に体重を預けて眠る。眠りが浅かったというソハヤが、今は己の側で無防備に、けれどしっかりと眠っている。
その事実は大典太にとって嬉しいものだった。きっと、己だけに見せている態度。
そう思えば今日一日抱えていたもやもやが晴れ、違った温かさが胸を満たした。
夕飯を食べ湯浴みを終えた後、大典太はソハヤと二人きりの寝酒をしていた。長時間遠征の労いを兼ねての寝酒で、昨日今日の互いの話を肴に日本酒を飲み交わし、小瓶が空になる頃には二振りともほどよく酒精がまわり、良い気分だった。
少し肌を赤く染めて、いつもよりも力の抜けた笑顔を浮かべているソハヤは、寝酒を始める前に敷いた布団へ横になる。
「よく眠れそうか?」
「そうだなぁ、いいゆめ、みれそう」
眠気がきているのだろう、目を閉じて告げる声は眠そうに少しだけ舌っ足らずで、それが幼く見える。己はまだ飲み足りないが、ソハヤは長期遠征から帰ったばかりだ。それに遠征先であまり眠れていないのならば、早く寝させた方がいい。もう今日はここでしまいだと、猪口と瓶を部屋の隅に片付けた。
「寝酒すると、ぐっすり寝れるんだよなぁ……」
天井の明かりを消そうとしていた大典太は、その声に下を見る。尻すぼみした言葉は、そのまま寝入りの言葉になったらしい。暫くじっと見ていてもソハヤはそれ以上何を言うでもなく、大典太はソハヤが寝てしまったことを知る。
明かりを消して、大典太もソハヤの隣に敷いていた布団へと潜り込む。
「……初めて聞いたな」
寝酒が睡眠を助けているなど、初めて知った。今日はソハヤについて初めて知ることが多い。
思い返してみれば、日を跨ぐ跨がないにしろ、長期遠征の後はよく寝酒を飲んでいたと思う。大典太が酒を嗜むので単に付き合いで飲んだこともあるだろうが、睡眠の補助としての意味合いもあったのだろう。
実際に深く寝入っているのかどうかは大典太には分からない。鯰尾はソハヤの眠りが浅かったと言うが、己はしっかりと寝ているソハヤしか知らないのだから、比べようもない。
ふと、大典太は身体を横向きにして、寝ているソハヤをじっと見る。太刀なので夜目が利かないが、全く見えないわけではない。短刀や脇差たちより劣るというだけで、目が闇に慣れれば輪郭くらいは分かる。ソハヤは規則正しい寝息をたてて、しっかりと寝ているようだった。
遠征中は他のものの気配で起きていたらしいが、大典太が姿勢を変えてもソハヤが起きることはない。投げ出された手に己の手を重ねてみても、起きる気配はなかった。それが嬉しい。
どこまでやれば起きるのか。どこまでが起きない範囲だろうか。先程は寝させてやりたいと思っていたのに、それを邪魔するようなことを思ったのは、大典太も己で把握しているよりも酔っていたからかもしれない。
寝ている横顔に触れてみる。起きない。頬を撫でてみる。起きない。顔の輪郭をなぞり、首筋を撫でる。少し身じろぎはしたものの、起きない。
投げ出された手に振れる。起きない。夜着の袖の中に手をいれ、腕をなで上げる。起きない。手を握る。起きない。手から少しの霊力を流す。
「んん」
小さく声を漏らして、ソハヤの目が開いた。寝起き特有のぼんやりした視線がこちらを向いたことが分かる。
「きょうだい?」
「……すまない、起こしたか。疲れているようだったから、霊力を分けていた」
「ああ……ありがとな」
「寝てていいぞ」
半分も開いていなかった目は、大典太の声に従い、素直に閉じられる。そうしてまた、すぅ、と穏やかな寝息が聞こえてきたところで、再び霊力を流してみた。今度は薄く、ゆっくりと。
流した霊力はソハヤの表面を包むように広がり、ソハヤ自身の霊力と馴染んだときには、ソハヤの気配が一段と穏やかになるのが分かった。
「……兄弟」
呼んでみても、応えはない。しっかりと深く寝ている。
他のものの気配に敏感で眠りが浅いソハヤが、大典太がいても深く寝入っている。気を許されているのだと嬉しくなる。
己の霊力を、己の存在を受けいれてくれた、と思った瞬間に湧き上がったのは歓喜と、それから腹の奥にくすぶっていた熱だった。
突然湧き上がった熱に少し驚いたが、その熱には覚えがある。いつか感じたことのある熱に記憶を辿ってみれば、初めて真剣必殺を出した日に辿り着いた。
初めての真剣必殺で霊力を放出した大典太に、同じ部隊になった刀たちは誰も近寄ることはなかった。大典太の抱える強大な霊力は、封じられていた蔵の屋根に止まった烏さえも殺す力のあるものだ。その霊力に明らかな意思を乗せて放出した霊力に触れれば、たとえ付喪神といえど無事では済まないことは分かっているのだろう。真剣必殺の興奮冷めやらぬ大典太を皆が遠巻きに見ている、という状況を漸く把握できたとき、大典太の沈み込もうとする気分を吹き飛ばすようにソハヤが声を上げて近寄ってきた。
「すごいなぁ、兄弟!」
普通に近寄り、あまつさえ肩に手をかけるソハヤに大典太は驚いた。驚いて、けれどほっと安堵する。続いた「無理すんな」という労りの声に、この兄弟はどんなときでも己を受け入れてくれるのだと確信した。
その時に身体を支配していた熱と、いま己の腹の奥にある熱はよく似ていた。この、胸が苦しくなるような熱の名を、欲、と言うことを大典太は知っている。
思えばソハヤは、手合わせでも遠慮はいらないと煽り、己も他の刀との手合わせよりも力を出すことが多かった。そして、己を兄弟と言って憚らない。最初から、己を受け入れてくれていた。大典太光世という刀を見てくれていた。
ならば、この兄弟は果たしてどこまで己という存在を受けいれてくれるのだろうか。
そんな疑問が浮かんでしまったのは、やはり酒のせいだ。
ん、とソハヤが寝息を漏らす。それに誘われるようにして、大典太は唇に手を伸ばした。
己の欲も、受け入れてほしい。はっきりと自覚した瞬間だった。
そこから大典太は夜にソハヤに触れるようになった。
起きているときに触れてもソハヤは許してくれるだろうが、けれど本意でなくとも意思の力でどうにでもなる。そういう刀であることを知っているので、夜の寝ている無防備なときに触れて試してみようと思ったのだ。その考えも後から思えばなかなかおかしなことではあったが、その時の大典太はそれがいいと思っていた。
最初は顔や腕、足先に触れるだけだった。肌の感触を楽しみながら、ソハヤが反応するところを探すように身体に触れていく。己の霊力が側にあるとより深く眠ることができるということが分かってからは、意図的に最初に霊力を流し込むようにした。
無意識の時に行為に及び、どこまで許されるかを知りたいと言いながら結局保険をかける己に自嘲したが、起きて拒絶される恐怖は拭えず、欲に突き動かされるように触れ始めてからは、少し強めに霊力を流し込むようにしている。
強めに霊力を流し始めた当初は、霊力が朝までソハヤに残っていることも多かった。ソハヤも起きた時に大典太の霊力が纏わりついていることを不思議に思っていたようだったが、何度か繰り返すうちに気にしなくなっていった。
頬、耳、首、鎖骨、胸。腹、腰、太腿、脛、足。
起こさないように慎重に、大典太は眠るソハヤの体に触れる。触る箇所がどんどんと増えていく。この頃は手で触れるだけでなく、唇や舌でも触れるようになっていた。
「……はぁっ……」
部屋に落ちる小さな息は大典太のものだ。胸に埋めていた頭を上げ、ソハヤの顔を一度覗き込んで安らかな顔に起きる気配がないことを確認すると、割り開いた足の間に腰を据えて下着をずり下ろす。手慣れた手つきで下着を足から抜き取り、太腿を僅かに開いた。
夜毎に繰り返される触れ合いに慣れたのか、日中の触れ合いが少し増えたからか、こんな大胆なことをしてもソハヤは身じろぎすらしない。そんなソハヤと対象的に、大典太は腹の奥の熱を抑えられなくなっていっていた。
ソハヤの中心部、陰茎に手を触れる。さすがにぴくりと震えが走るが、今日もソハヤは起きはしなかった。そも、この震えは己の手が触れたことによる違和感での震えではなく、期待からくる無意識の震えであることは、大典太には分かっていた。
今日のこれまでの行為で、ソハヤの陰茎はほんの少し硬い。ソハヤの方も、ただ感覚を受け入れてくれているだけでなく、己が触れることに快感を得るようになっていた。
頭の奥では、このままではいけないという己の理性が必死に声を上げていた。けして綺麗ではない欲を、劣情をソハヤに向けている罪悪感もある。
初めは己を受け入れてほしい、という思いだった。この行為で起きないのならば己を受け入れてくれているのだと、そう考えていた。
いつからか、それが逆転していた。この行為をしたいがためにソハヤを起こさないように、ゆっくりと慎重に触れるようになった。触れる前に霊力を馴染ませていたのもそのためだ。臆病だったのではない、最初から浅ましい思いでソハヤに触れていたのだ、と気づいたのはいつ頃だっただろうか。
けれど、もう既に引き返すことはできない所まで来てしまっていて、それに最初から、己がソハヤへ向ける欲はこうして熱を与えたいという気持ちも含まれていたのだ。今更止まれないと、今も尚頭の片隅で止まれと告げる理性を無視して熱に溺れていく。
まだ柔らかく垂れている竿を丁字油をまとわせた手で握り込む。陰茎が震え、ふるりとした震えに誘われるようにしてして己の腹の奥の熱も暴れ出す。は、と一つ息を吐いて熱を宥めてから、手を動かした。根本から先へ、先から根本へ。痛みを感じないよう丁寧にゆっくりと陰茎を擦ると、次第にぐちゅぐちゅと水音が混じようになる。少し強めに裏筋をなぞれば、びくりと陰茎が震えて先走りの液が溢れ出る。
己が与えている刺激に対しての返答としては、これ以上ないくらいだ。
ここに触れるようになってどれくらいが経ったか。男性体の弱点でもある陰茎を弄っても、ソハヤは眠り続けている。眠りながら快感を高められ、ついに口から熱を孕んだ息が漏れ始めた。
「んんっ……ぅ……」
水音と吐息が、静かな部屋に満ちる。心なしか部屋の空気も熱っぽく感じる。亀頭の先端を親指でくるくると撫でると、ソハヤが息を飲む音がした。それでも、静止の声がかかることはない。
「あ、ぁ、んっ……」
大典太はソハヤの陰茎を扱く手をそのままに、もう片方の手で臀部に手を伸ばす。溢れた先走りの液が伝って、後孔の周りは濡れそぼっていた。ひくついた穴に、誘われるまま指を一本差し込んだ。
「ふっ……!」
昨日も解していたが、今日もまだ中は固い。一度指を抜いて丁字油をまとわせてから再度侵入すれば、きゅうと締め付けながらも、中は熱く大典太の指を迎え入れる。先程よりは滑らかに奥まで入った指で、内壁の柔らかさを確かめるようにぐにぐにと動かす。抜いて、入れて、丁字油を足した二本の指で中を擦り上げた。
「っン!」
広げるように、二本の指を動かす。まだまだ狭いが、中で快感を拾えるようになってきているらしい。後ろだけで慣らしていたときはそうでもなかったので、前と後ろと同時に触れたのが良かったようだ。
ソハヤの身体を、本刃の預かり知らぬところで開拓していく。その背徳感に背をぞわぞわと粟立たせた大典太は自身の口角が上がっている事に気づかず、与えられる快感から逃れようと上へ上へとずり上がっていくソハヤの身体を抱きとめて、ソハヤの中を開く行為へと没頭した。
「おー、また派手にぶちかましたなぁ。男前だぜ兄弟」
転送門をくぐって戻ってきた本丸で、大典太はにやにやとした顔に出迎えられた。つい先程まで居た殺伐とした戦場とは打って変わっての呑気な声に、僅かに苛立って思わず睨めつける。けれどそれを、威勢がいいな、の一言で片付けたソハヤは、ぴりぴりと殺気立つ気配を物ともせず大典太に近づいて、その身を抱きしめた。
「っ……!」
真剣必殺を繰り返し、重傷になっている大典太が呻くのに関わらず、ソハヤは大きな身体をぎゅうぎゅうと抱きしめる。
「そんなに殺気づいた霊力ビリビリ出してちゃ、一緒に手入れ部屋に入ったやつを驚かせるだろ」
「ああ……」
今日の戦場は久しぶりに酷かった。延享の記憶、江戸の市街地。出陣が可能になってからまださほど経っていない合戦場は敵が今までより強く、極短刀を入れての進軍でもなかなか思うようにいかなかった。高速で動く槍に翻弄され、皆が皆、負傷した。大典太も真剣必殺に次ぐ真剣必殺で、なんとか敵を倒すことはできたが、隊長の判断で帰城となった。
重傷のものは既に手入れ部屋に運び込まれている。大典太も手入れ部屋にいかなければならなかったが、真剣必殺の後遺症とでもいうべき、霊力の放出と興奮が収まらなかった。帰城までの間、隊員たちが己の霊力を気にして遠巻きにしていたことにも気づいていた。どう扱っていいか分からない、という戸惑いの視線に構う余裕は大典太にはなかった。
ソハヤの言う通り、落ち着かせなければ手入れ部屋に行くのは憚られた。大典太は大人しく腕の中に収まって、されるがままにする。門の前で太刀二振りが抱きしめ合っているのは邪魔になるだろうが、本丸の皆は慣れたもので「手入れ部屋開けて待ってるから、終わったら早く来るように」と言い残して各々建物へと戻っていった。
触れたところから霊力が落ち着いていくのが分かる。ソハヤへ吸収されているのか、それとも二振りの霊力が混じり合っているのか。毎夜の触れ合いで己たちの霊力の境が少し緩くなっているのだろうか。そんなことを考えながらソハヤの肩へと顎を乗せて力を抜いた大典太の身体を、ソハヤはしっかりと受け止めてくれた。
また、ソハヤは己を受け入れてくれた。どんな己でもきっと、あの行為も、ソハヤは受け入れてくれるのだろう。毎夜の行為を思いだして、腹の奥がずくりと重くなった。
「兄弟、頭に鳥の羽根ついてる」
「鳥……」
大人しくなった大典太に笑って頭をわしゃわしゃと撫でていたソハヤが、ほら、とその羽根を見せてくれた。濡羽色の羽根はからすだろうか。
「今日の記念だな」
何がだ、と言いながら差し出された羽根を思わず受け取ってしまう。そろそろ落ち着いたか?と問うソハヤにはもう少しと首を振って、大典太は欲に感づかれないようにそっと首筋に鼻先を埋める。ずくずくと腹の裡が疼くのをどう処理しようかと考える獲物を狩るような目は、誰にも見られることはなかった。
夜。薄ぼんやりとした明かりに照らされた室内で、大典太は眠るソハヤにいつものように触れていた。
「はぁ……、っ、」
己の陰茎を扱く手を早めれば、ぐちゅぐちゅとした水音がより大きく響く。声を殺し快感を追いながらも、目だけはしっかりとソハヤを見つめたまま、熱を高めていく。
大典太の陰茎を扱くのは、大典太の手よりも少しだけ小さいソハヤの手だ。力の抜けたその手から陰茎が滑らないように、力を込める。扱く手の動きはいつもの自慰とあまり変わりないが、握っているのがソハヤの手というだけでひどく興奮する。他人の体温で致すのが非常に気持ちがいい。ソハヤも気持ちいいと思っていてくれるのだろうか。聞くことは出来ないが、反応してくれるので同じような気持ちだろう。
「くっ……もう少し……っ」
手を強く握り、ぐちゅぐちゅと動かす。出る、というところで、筒状にしたソハヤの手のひらに己の熱を放出した。
「っ……はぁ……」
出陣の後からくすぶっていた熱が、少しだけ引いた気がした。
ソハヤに霊力を宥めて貰って手入れ部屋に行ったが、札を使って瞬時に手入れが終了した後も、出陣後の昂ぶりは収まらないままだった。夕飯を食べ終え、ソハヤとの寝酒を楽しんだ後も、腹の奥ではずくずくと熱が燻ったまま。その熱をどうするかは、今の大典太には一つしか方法が考えられなかった。
いつもより逸る気持ちを抑えて、いつもより制御の利かない霊力を流し込み、夜着をはだけさせた身体に触れるよりも先に、大典太はソハヤの手で自慰を行った。それでも、興奮は収まる気配がなかなかない。
「…………」
ふと、視線がソハヤの下半身へと向く。まだ下着に包まれたままの、そこ。そこの熱を思い出し、ごくりと無意識に喉を鳴らして、ソハヤの手に吐き出した精の処理もそこそこに、大典太はソハヤの下着を脱がす。
いつものように陰茎と後孔を同時に弄れば、日頃の慣らしのおかげかすんなり指が三本まで入った。丁字油を多めに後孔へと注いだのもあるかもしれない。
「ふっ……」
熱い壁を指の平で擦り、感触が他と違う場所で指をとんとんと突けば、動きに合わせるようにして熱い息が漏れる。
「あっ!」
甲高い声が部屋に響いた。防音も兼ねている室内用結界を張っているので、その声は外へは聞こえることはない。全部屋に導入されているそれは霊力の加減で様々な効果が付与されるので、とても便利な結界である。
「んっ、はぁ……んん」
三本の指をばらばらに動かせるようになる頃には、ぐちゅぐちゅと響く水音が陰茎からなのか後孔からなのかわからないほどになっていた。
ここまでしてもソハヤは一度も起きたことがない。自身の預かり知らぬところで快感を高められ、暴かれるソハヤに、粘度の高い熱がぞわりと背を抜け頭を揺らし、腰を重くする。
ソハヤから手を離すと、大典太は己の前をくつろげ、自身の陰茎を取り出した。既に硬く大きく勃ちあがっている陰茎は、触ってもいないのにぬらりと濡れていた。
「……はっ……、兄弟……、ソハヤ」
もう我慢もできそうにない。熱に浮かされた頭でソハヤの名を呼ぶ。これからされることなど気づきもしないで、ソハヤは眠っている。いつもより眉間の皺が寄っている寝顔は、けれども己がこれからする行為に反して酷く穏やかに見える。
後孔をぐちゃぐちゃにされても起きないのだから、己の陰茎を突き入れてもソハヤは目を覚まさないだろう。
丁字油をまとわせ、先走りを滲ませる先端を、ソハヤの後孔に押し当てる。
起きてくれるな。己を受け入れてくれ。
腰を抱き、ぐ、と力を込めた。
「………あ……?」
そんな間抜けな声が聞こえてきたと同時に、ぐぷりと音を立てて大典太がソハヤの中に押し入った。
「ひっ……!? いっっ………っ~~~!!」
勢いよく最奥まで大典太が入り込むと、ソハヤの身体が大きく跳ねた。ぐずぐずに溶けた中の熱さを味わうより先に、まるでねじ切らんばかりに陰茎を締め付けられた。
「っ……!!」
痛みすら感じるほどの締め付けに歯を食いしばって耐えた大典太は、ふぅふぅと息を吐いて、落ち着かせるようにソハヤの腰を撫でる。
「いっ、ひ、ゔああああ………っ、」
「きょう、だいっ……」
声に顔がこちらを向く。涙が滲んだ目と、視線が合った。ひゅ、と飲み込んだ息はどちらのものか。
「は、あ、え、なにっ……」
起き抜けに身体に与えられた感覚に混乱しているのか、ソハヤはしきりに頭を振る。なに、と問う声は弱々しく、時折痛ましい声が混じった。
ついにこの時が来てしまった、と胸に冷たいものが広がる。その冷たさに幾分か頭が冷静になり、とりあえずは中の締め付けを緩めなければ辛く、落ち着かせるようにソハヤの腰を撫でた。
「んぁっ……、……はぁ……っ!?」
自身の上げた声に驚いたソハヤの目に、理性が戻る。その目に見られるのが怖くて目を逸らし、気を逸らすためにソハヤの陰茎を握った。衝撃にか少し力をなくしてしまっていた陰茎は、元々開放直前まで高めてあったせいか何度か擦り上げると力を取り戻し、大典太を締め付けていた後孔も緩んだ。
「やめ、兄弟、んぁっ……なに、ひぅっ」
突然与えられた快感に、ソハヤがまた混乱したように声を上げる。痛々しいものばかりではなくなった声に少し安堵しているうち、きゅう、と内壁が蠢いた。
「あっ…!? きょ、だい、」
先程の締付けとは違う、やわやわと大典太を喰むようなその動きに、胸にあった冷たさを凌駕するような熱がぶり返す。熱く絡みついてくる内壁が、酷く気持ちがいい。
「兄弟……っ、」
ぶり返した熱は、理性を焼いた。
「いっ、うぁっ、あっ……!! なん、でっ……!」
ずるずると半ば程抜いて、その刺激に逃げようとする腰を両腕で引き寄せ、どちゅりと最奥を突く。
「ぅぁあっ、あっ! や、めっ……!」
中が熱くて狭くて気持ちよくて、熱に浮かされて引き抜いては突き入れてを繰り返す。丁字油と先走りがソハヤの中で混じり合い、大典太が抽挿を繰り返すたびにいやらしい粘着質な音を部屋に響かせる。そのうち漏れ出てきたそれらがソハヤの臀部を濡らし、肉と肉のぶつかり合う音もぷちゅ、ぐちゅ、というような音に変化していった。
「んく、ひっ、あっ、んぁっ……っ~~~!!!」
「ソハヤ……!……きょう、だい……! くっ……!!」
ごりごりと内壁を押し潰すようにしていると、気持ちいいところにあたっているのだろう、時折びくびくとソハヤの身体が跳ねた。熱を孕んだ嬌声を上げて、けれど嫌だと言うように頭を振る。大典太の動きを止めようと腰を抱く腕を掴もうとするが、その手がぬるりと滑って掴むことができなかった。ああ、処理をしていなかったなとぼんやりと頭の片隅で思いながら、裡に渦巻く熱を、欲を、追いかけて、高めて、受け入れてほしくて、腰を振る速度を早くする。
「あっ、やだ、あ、ああっ……!!」
「ぐっ……」
「っ~~~~~!!」
ソハヤの身体を掻き抱いて一際強く最奥を穿ち、頭が白くなる快感のまま大典太はソハヤの中で熱を吐き出した。
「……っ、はっ、はぁ……っ」
荒い息を整えるように大きく呼吸を繰り返していると、ぐ、と己の身体を離そうとするような力を感じた。顔を上げれば、頬を上気させながらも眉間に皺を寄せた険しい顔と視線が合った。すぅと頭が冷えていく。
「…………ソハヤ」
気づかれてしまえば、己のこの行為は受け入れられないだろう。拒絶される、と恐怖にも似た感情が湧き上がるのを感じながら沙汰を待つ。
「……っ、抜け、よ。気が済んだなら、もう良いだろ」
「あ、ああ……」
「んぅ……っ、俺は、こんなところまで、っ、許した覚えはねえぞ……くっそ、触れるだけだから放っておいたってのに」
ぴたりと大典太は動きを止める。抜けかけていたそれが急に止まったことで余計な刺激が生まれたらしく、ひ、とソハヤは喉を震わせた。
「……気づいていた、のか?」
少しの間を置いて、ソハヤが首肯する。
「兄弟が顕現してからちょっとして……顔とか、首とか……手とか触ってただろ。兄弟だし、寝てる時に触るだけなら、いいかって、思ってたんだよ。まさか、ここまで、」
その後の言葉を、大典太は聞いていなかった。
気づいていて、けれど己が触れるのを止めることはなく、許して受け入れてくれていたらしい。寝ている相手にべたべた触れるという特殊な状況を、怒るでもなく、己だからと許していた。その事実に胸に湧き上がるのは、安堵と歓喜だ。
「……霊力を流し込んだことは」
「気づいてたさ。っていうか、気づかないほうがおかしいだろ。でも、俺の霊力を上書きしようとか、そういうことを考えてるわけじゃなさそうだったから」
「許してくれたのか」
「……まぁ、悪い気は、しなかったし」
目を逸らしながら歯切れ悪くぽつりと呟かれた肯定の言葉。大典太はしばし固まって、戻った思考がそれが意味するところを理解すると同時に、身体全体に熱が広がっていくのを感じた。
大典太が霊力を流し始めたのは、ソハヤに劣情を持って触れるようになってからだ。己が触れていることに気付いていたソハヤが、急に自身から感じるようになった大典太の霊力の意味するところに気付いてもおかしくはない。目を逸らして、珍しく歯切れも悪いその様子が、答えではないだろうか。
「はっ!? でかくすんなっ、抜けって……!」
抜く途中で中途半端に止まったままだった陰茎の変化を如実に感じたらしいソハヤが、思い出したようにじたばたと暴れる。暴れると余計に意識するのか、眉を寄せて顔をしかめる。
「……兄弟」
「なに、」
大典太の霊力を感じながら、それが意味することに感づきながら、放置していた。つまり、それは。
どこまで許してくれるのかと境界を慎重に探っていたが、もうとっくにソハヤによって境界は取り払われていたようだ。
「気持ちよくしてやる」
は?とソハヤが返すよりも早く、大典太は再び自身を奥まで突き入れた。中に放った己の精が出すぐちゅりという音と、肉のぶつかるぱんという音が、ソハヤの嬌声に重なる。
「あああッ!!! ひ、ぃ、うぁっ……!!」
強すぎる衝撃に、ソハヤが首を反らす。ぴんと張った足を己の腰に回すようにして態勢を整え、未だ夜着が引っかかっている腰を強く掴む。
己の熱と快感を追った先ほどとは違い、ソハヤの反応が良い場所を腰を引く時に雁首で擦り上げ、穿つ時に亀頭で強く突き、ソハヤへと快感を与える。こうしてまぐわうのは初めてだが、今まで何度も後孔を攻めてきたのでソハヤの良いところは大体分かっているし、ソハヤもうまく快感を拾えているはずだ。その証拠に、上がる声は甘く、吐く息は熱を孕んでいる。
「あっ! きょうだ、っ、ぃあっ、あ!」
ソハヤを追い上げながら、大典太も快感を追う。部屋の中が、繋がった場所が、二人の熱であつい。
「兄弟、っ、ソハヤっ……くぅ……!」
「やめっ、もっ、くっ、ほんっと、しんじらんねっ、んあっ、ああ!」
嬌声の合間に漏らすソハヤの恨み言に、くつりと喉を鳴らした。雁首が出るほどにずるずると己を引き抜いて、早くと強請るように蠢く後孔に一気に突き入れて。与えられる感覚に見開かれたソハヤの赤い目を真っ直ぐに捉えて、言う。
「……だが、許して、受け入れてくれるのだろう?」
「っ~~~~!!」
熱に浮かされた目で睨めつけられても、迫力はない。最奥に亀頭を当てたままぐりぐりと腰を押し付ければ、精液と丁字油が混じった粘液が壁と亀頭の間で泡立ち、潰れる感触がした。それにも感じるようで、強い衝撃から逃げるように抱きついてきたソハヤの身体も汗ばんで熱かった。
狭く熱い泥濘は、酷く気持ちがいい。
腹の奥でぐつぐつと沸き上がっていた熱が、開放を求めている。ソハヤもそろそろ限界のようで、大典太の頭を掻き抱いて、だめだ、いく、と繰り返す。
ソハヤも感じてくれていることへの歓喜が、最後の後押しとなった。どちゅん、と音がするほど強く奥を穿つと、ソハヤが声にならない声を上げて吐精する。同時に熱い内壁にぎゅうぎゅうと自身を喰まれ、感覚も思考も真っ白になるほどの快感に、大典太も最奥へと再び熱を吐き出した。
「はっ、はぁっ……」
全てを出し切るまで腰を振り、どぷりと中へ注ぎ込みこむ。ソハヤの上に倒れ込まないように気力で上体を起こすと、ソハヤの腹の上にたまった白い液体に目がいった。精を吐き出したソハヤのものはくたりとしている。
一度目は陰茎に触れることで快感を得るように促していたが、今の行為ではそこには一度も触れていない。己を受け入れた中への刺激だけで、達したのだ。その事実に、心臓の音がうるさい。欲が、熱が、満たされていく。
放った精が己の体温と馴染んでいくの感じながら、大典太は己が裡に残った歓喜を伝えようと、ぼうとしているソハヤへと口づけた。
「すまなかった」
あの後すぐに気をやってしまったソハヤが目覚めた瞬間、大典太は大きな身体を小さくして謝る。ソハヤは暫く状況が掴めないようだったが、身じろぎをした際に思い出したのだろう、顔を赤く染めてじとりと大典太を睨んできた。その身は大典太が清めていて、行為の跡はその頬の熱と、潤んだ瞳くらいだ。
「……流石に、あれはないぜ、兄弟」
いつもより掠れた低い声は、怒っていると大典太に伝えてくる。
「放っておいたら調子に乗りやがって」
「すまない」
背を丸めて、もう一度謝る。
「許可なく触れてしまって」
「そこじゃねえだろ!」
べし、と枕が飛んできて、怒りのこもった枕を甘んじて頭で受け止める。落ちた枕をソハヤへ返そうと上体を起こすと、ソハヤが呻きながら身体を丸めていた。
「……痛むか?」
痛くないように慣らしたつもりだった。ここ最近は後孔を中心的に触って中を拡げていたので、己を受け入れても然程痛くはないはずだと思って尋ねれば、兄弟のでかいんだよ、と小さな声で怒られた。否、これは褒められたのだろうか。
「褒めてはないからな」
「……」
違ったらしい。
大典太は無言で拾った枕をソハヤに差し出し、ソハヤも呆れた顔をしつつも枕を受け取って、改めてぽすりと枕に頭を乗せた。そして一つ息を吐き出して、大典太を見つめる。怒気のない、真剣な顔だ。
「兄弟。申開きはあるか?」
真剣、というよりは圧をかける顔で、ソハヤが問う。
「……いや」
言い訳もなにも出来ないことは分かっていた。これは己の自分勝手な欲が起こしたどこまでも自分本位な行動で、ソハヤの意思を確かめることなくその身体を暴いたのだ。どこまで受け入れてくれるのか、どこまでも己を受け入れてほしい、そう思いながら、一方的に欲をぶつけていただけだ。それは認めるべき己の罪だ。
「すまなかった。……お前が、俺の側では深く眠れると知って、抑えが効かなかった。俺の霊力も受け入れてくれた。だから、俺の全てを受け入れてほしいと思った」
ぽつぽつと告げた理由を聞いたソハヤは、「あー」と細く呻いて、まぁ、と続ける。
「俺も、兄弟が何してるのかなんとなく分かってて放っておいたからな。その点では俺も悪いし……」
「兄弟」
己の一言に込められた感情を察したらしく、ひとつ睨め付けられる。
「許したわけじゃねぇぞ。ただ、この結果は俺が招いたことでもあるし、謝罪は受け入れようってだけだ」
それは許すも同義では、と思ったが、言えば機嫌を損ねて部屋を追い出されかねないので胸中に留めておく。
「分かった」
「ったく。今後は許可なくやるんじゃねえぞ。それにもう時代は俺等が打たれた頃じゃないんだ、こういう行為には手順が、」
「それなんだが」
「ん?」
「許可があればいいのか?」
「は?」
訝しげに見上げてきたソハヤはしばらくして漸く自身の失言に気付いたらしく、否定しようとしてか慌てて起きあがろうとして身体の違和感に呻き布団に沈む。
「お前は嫌とは言っていなかった。同意なく触れたのに、許して、受け入れてくれた」
「そんなこと」
「許可を取らなかったことにだけ、怒っている」
「っ、」
ソハヤが本気で怒って己を拒絶しようとするならば、今ここに大典太はいないだろう。部屋を締め出され、ソハヤの霊力によって接触を阻まれ、謝ることすら許されないまま、数日後には元のような兄弟仲に戻らせれた可能性があった。
けれどソハヤは、怒ることこそすれ、拒絶はしなかった。あまつさえ、お互いが招いた結果だと言う。
結局のところ、最初から大典太を受け入れてくれていたし、どこまでも大典太を受け入れてくれるのだ。
同意のないまま行為をはじめた己が言うのもおかしなことであるが、ソハヤはこと身内に対しては甘すぎる。大丈夫か、少し心配になった。
布団に仰向けになっているソハヤを横から覗き込んで、少し潤んでいる赤い目をひたりと見据えて一言。
「兄弟。許可を、くれないか」
一瞬何かを言いかけて、けれどただはくはくと動いただけの口が真一文字に引き結ばれる。大典太はその口から言葉が紡がれるのを、座して静かに待つ。
「……許可が欲しいなら、それ相応の誠意ってものを見せてくれよ」
それはある意味許可が出たようなものだ。大典太は小さく口元を緩め、沸き上がってくる歓喜につい伸びてしまった手は、ばしりといい音を立てて叩き落とされた。