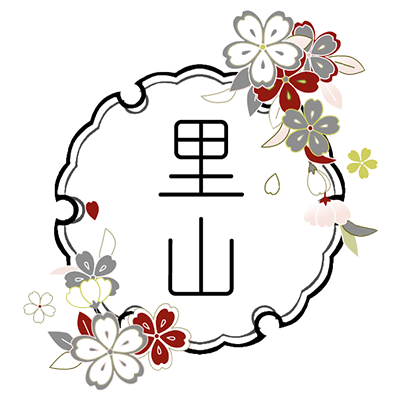縋る手の先 サンプル
SAMPLE
審神者によって顕現し、人を模した身を与えられた付喪神である自分たちだが、その熱を発散させる方法は知識として持ち得ていた。人として形を取るならばそれに付随する様々な現象や症状に対応できる知識がないといけない。故に、顕現するときに知識を与えたと、この本丸に来た最初の頃に審神者から聞いていた。また、経験のない記憶を辿れば、元の主達がどのようにして燻る熱を発散させていたかを知った。
この方法が互いにとって良いのかどうかは判らない。だが、これしか熱を抑える方法を知らないのだ。
まだ、ていのいい性欲処理だと言えればよかったが、それをすることは和泉守の矜持が許さず、こうして苛立ちを抱えながらも熱を分け合う行為を続けてきた。初めは辿々しかった手の動きは熱を与えるようになり、痛みばかりだった繋がりは快感を生む行為へと変わった。
目的を持って既に乱れていた寝巻の襟から手を入れ、両の肩をむき出しにする。寝巻を引っ張れば腰紐も緩んでいたのだろう、簡単に合わせが開いて上半身があらわになる。
手入れを終え共に湯浴みをした時にも確認したが、しっとりと汗ばむその身体には、傷ひとつ残ってはいなかった。手入れ部屋に入ったので当たり前ではあるが、それでもあれだけの大きな傷を負っていたことを知っている身としては、改めて確認をしないと落ち着かない。背へと手を回し入れて確認するが、滑らかな肌の感触が返ってくるだけで、傷のようなものは感じられなかった。
「んんっ……」
傷を確認する手の動きに感じたのだろう、陸奥守の背がしなる。しがみついてくる様に心臓がどくりと脈打ち、和泉守は背に回した手を、そのまま背骨の窪みに沿って滑らせた。手が肌を撫でる度に声を震わせる陸奥守に気を良くして、肉刺の出来たざらついた手の平で背中を弄る。
何度か背骨をなぞった後、上から下へとその手を滑らせ、ゆるく纏わりつく腰帯の境界を越えて臀部の割れ目と触れた。
「……っ」
ぎくり、と身体が固まる。それに気づき手を離せば、ほうと安堵するような息が漏れた。
何度か身体を重ねてはいるが未だ行為自体を認めていないためか、肝心な場所へ触れようとすると陸奥守の身体は強張る。受け入れることを許したというのに、最後のあがきとばかりに身体を強張らせる。その身体を宥めすかして熱に溺れさせ、そうして漸く陸奥守は己が熱を受け入れるのだ。
強張る身体が自分を拒絶しているように見えて、無理矢理にその身を暴いてやろうかと思う時もある。けれどそれをしてしまえば、陸奥守は和泉守に縋ることを止めるだろう。それは避けたかった。
何故そのようなことを思うのか、何故縋られることを嬉しいと思い、何故縋って欲しいと願うのか。何故、こうも苛つくのか。
そこに根付く感情はどのようなものなのか、それは未だ判らない。否、判らない振りをしている、だけかもしれない。ぼんやりと形作られる何かを振り払うように、和泉守は身体を起こす。その動きで陸奥守の手が背中から離れたことを惜しく思った。
一旦離れた陸奥守の手は今度は腕に回され、戸惑うように見上げてくる目と視線があった。その瞳は熱に流されながら、どこか痛みのような揺らぎを見せる。
陸奥守にしてみれば、この行為は不本意なのだと改めて思う。弱っているところを見られ、差し出された手に頼るしかなく、あまつさえ、その相手が新選組の刀であった和泉守である。だが、それを全て飲み込んだ上で、行為に至っている筈だ。遠慮することなく裾を割る。
そこは形を主張するように盛り上がっていて、下帯の上から触れれば既に固くなっていた。何度か優しくそこをなで上げると、ひくりと足が震える。閉じようとする足の間に自分の身体を滑り込ませ、閉じられないようにした。
「ひっ、」
ぐ、と握りこむように盛り上がりを掴めば、小さな悲鳴が聞こえた。何度かそこをやわりと揉み込んでいるうち、吐き出される息に艶が混じるようになる。
「んっ」
「腰上げろ」
僅かに湿ってきた下帯を外そうと結び目に手を這わせた和泉守に答えるように、陸奥守が僅かに腰を浮かせた。結び目を解いて外した下帯の下で、陸奥守の陰茎は既に形を変えている。腰の下から下帯を取り布団の隅に放り投げてからそれに触れれば、陸奥守は体を震わせて腰を落とす。
ゆるく立ち上がった陰茎に手を這わせ下から撫で上げていくと、直接的であるが緩やかな刺激に嫌々をするように陸奥守が頭を振る。熱くなったそれを握るようにして手を動かし、鈴口を指の平で強く擦った。
「ぅあっ」
強い刺激に耐えられなかったのか、漏れ出た高い声にはっとして、陸奥守は唇を噛む。声のみならず呼気さえ漏らすまいと強く噛まれた唇は、けれど和泉守の手の動きに小さく開いていく。は、は、と漏れる息は熱く、それが和泉守の熱を煽った。
すっかりと形を変え酷く熱く熱を孕む陰茎を、和泉守は追い上げていく。いつしか手を動かす度に粘着質な水音が響くようになり、その音に羞恥を煽られるのか陸奥守が顔を反らし布団に耳を押し付ける。擦る手の動きを早くすると、腕に回された手が強く握りしめられた。
「っぁ、ん、……やっ、いず、み」
「ん。ほら、一回いっとけ」
「っ……ひ、っんん……!」
引かれる腕に促され陸奥守の陰茎を荒く早く扱いてやれば、身体を硬直させて熱を吐き出した。ぴちゃりと飛んだ白濁した熱は、陸奥守の腹と和泉守の手を汚していく。力の抜けた身体は荒く呼吸を繰り返していて、けれど和泉守の手が触れたままの陰茎は未だ熱を持ち続けている。
「陸奥」
達した余韻で呆けていた陸奥守の名を呼ぶと、ただ熱だけを湛えた陽色の瞳がぼんやりと和泉守の顔を映す。呼吸のために薄く開いたその唇に誘われ、上体を倒して顔を近づける。軽く触れてから下唇を喰み、柔く歯を立てた。
戯れのような口吸いに、陸奥守の腕が首へと回される。軽く引き寄せられて、口吸いが深くなる。
陸奥守の意識が口吸いに向かっている隙に和泉守は枕元へと手を伸ばし、水差しと共に持ってきた丁字油の器を手に取った。蓋を開けて指を油に付け、その指で後孔に触れる。一瞬身体が跳ねるが、構わず指を一本中へ潜り込ませた。