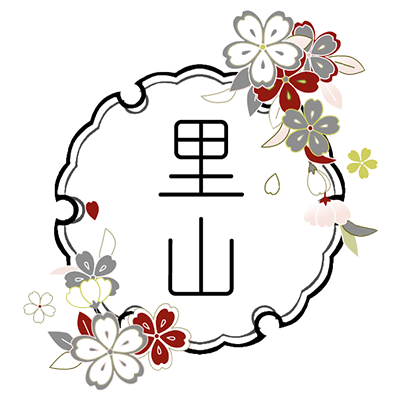青に揺蕩い、赤に消え 上 サンプル
SAMPLE
「和泉守、余裕だなぁ」
そんな三人を見て、厚がぽつりと呟いた。厚も最近漸く戦に出させてもらえるようになった一人で、戦に出るのは三回目だという。
「俺、初陣の時そこまで余裕なかったもん」
「緊張はしてなかったのは流石だったけどな」
「まぁオレは元々前の主に使われてたからな。こういう大規模な戦は経験したことがないが、切って殺すのはお手の物、ってやつだ」
「おんしはもうちっくとばぁ、緊張したほうがええと思うけんど」
「ああ?」
「もう、陸奥守さんも兼さんも、ここは戦場なんだから、」
言いかけた堀川が、そこで言葉を切る。他のものも気づいたようで、それぞれが表情を一変させた。瞬時に場の空気が変わる。本丸での和気藹々とした雰囲気を引きずっていた空気が張り詰める。
「薬研、厚は偵察へ。堀川は周囲の様子を」
「了解」
「任せろ!」
「兼さんはここにいて」
緊張感を持って発せられた陸奥守の号令で動き出した三人が戻ってくるまでには、そう時間はかからなかった。敵は五体、合戦場へと向かっている。周囲には人の気配はなし、迎え撃つ場所が近くにある。
「ほいたら、厚と薬研と堀川が前へ、わしと和泉守が後ろから行くき」
いいか、と確認するように陸奥守が視線をよこす。敵がいるという緊張感に陸奥守はいつもの笑みを消し真剣味を帯びた顔つきをしているが、けれど強い視線は初陣の和泉守に対して不安を訴えてくる。それに頷くことで問題はないことを示すと、改めて指示を出す。その横顔は隊長としての顔つきで、殆ど笑顔しか見たことのない和泉守には見慣れない表情だった。だがそれも陸奥守らしいといえばらしかった。
敵に気づかれないように移動し迎え撃つ予定の場所まで来ると、それぞれが陣形を組む。この地に来た時に感じた戦場の気配ではなく、敵の殺意や激情が肌を焼くかのように感じられ、知らず和泉守は刀を鳴らした。
「焦るなや」
小さなその音を聞きつけた陸奥守が言う。
焦ってはない。ただ、戦が始まる前の張り詰めた空気に、緊張感が高まっていく。
わあ、と風に乗って遠くの合戦の喧騒が聞こえてきた時、敵が姿を現した。禍々しいまでの殺気と入り交じる憤怒や後悔などが渦巻いて、辺りの瘴気を濃くする。和泉守は唾を飲んで、緑色の炎のようなその異形の姿を見つめた。
敵がこちらに気づく前に、前にいた三振りが駆け出していた。薬研と厚が足の速さを生かしながら敵を撹乱し、堀川も敵の一体へと食らいついた。二体は薬研と厚が引きつけ、残りの二体を陸奥守と和泉守が受け持つ。
三振りに続くように駆けていた陸奥守が足を止め、僅かの間を置いてから、ばん、と突然破裂音が響く。突然鳴った音に驚いてそちらを見れば、陸奥守が敵を見据えて銃を構えていた。そういえばこいつの戦法は銃の先手必勝だったかと思い出し、和泉守はすぐに意識を敵へと向ける。
陸奥守の撃った弾を受けただろう敵が傾ぐが、それでも致命傷とまでは至っていない。だがあの傷ではすぐには動けまいと、和泉守はもう一体の方へと向かう。
抜身の刀を振り上げ、敵の胴を斬りつける。その衝撃で僅かに後ろに傾ぐも、それだけだ。ぱくりと開いた胴の痛みに呻くように唸り声を上げて、敵が刀を振り上げる。
ちぃ、と舌打ちをしてその場を飛び退き、すぐに態勢を整えて振り下ろされた敵の刀諸共その腕を切り落とした。人であれば肉と骨に阻まれるだろうが敵の腕は骨ばかりで、多少の抵抗は刀へと力を乗せることで対抗した。腕を切り落とした刀を返して、がら空きだった胴をもう一度斬りつける。肩から腹まで袈裟懸けに斬りつければ、肉に刃が食い込む感覚が刀を通して伝わってくる。ぐ、と押しこむように斬りつけ、赤を散らした。
恨みと憤怒を撒き散らしながら断末魔の叫びをあげて、敵が地へと倒れ伏す。ぱきぱきと硬質な音を立て崩れていく敵を睨めつけながら、刀に付いた血を振り払った。敵を倒したことに肩の力を抜こうとした瞬間。
「兼定!」
名を呼ばれ、はっとして振り向くと、こちらにに向かってくる敵が見えた。考えるよりも先に身体が動き、身体を反転させる力を利用して斬りつける。怯んだそこへ畳み掛けるように刀を横に一閃すると、確かな手応えを感じた。ぐ、あ、と声にならない声を震わせて、敵が崩れ落ちていく。
「すまねえ、和泉守! 大丈夫か」
焦ったように走ってくるのは厚だ。どうやら厚が取りこぼした一体が和泉守に向かってきたようで、酷く申し訳無さそうな顔をしている。刀身に付いた血を拭い鞘へ収めてから力を抜くように息を吐き、走り寄ってきた厚に向き直って別になんともねえよと言えば、よかったと胸をなでおろす。
辺りにはもう敵はいないようで、瘴気は完全に消えていた。場に残る血の匂いだけがやけに気になって、ひくりと鼻を鳴らす。この姿になって初めて嗅いだ血の匂いは、いい匂いではないが馴染んだものだった。
「けど流石だな、和泉守の旦那。背後からの敵にも反応できるなんて、顕現したてじゃ難しいことだぜ」
とっさに反応できたことを、厚を追いかけてきた薬研に褒められて、和泉守はまぁなと笑みを浮かべた。手合わせはあくまで手合わせであって実戦めいたことはできなかったが、初陣で褒められるほどに動けたのならば手合わせも意味があっただろう。
「兼さん、ちゃんと動けてるみたいだね」
隣に立った堀川が、安堵の表情を浮かべて見上げてくる。
「あったりまえだろ。初陣でやられるほど弱くはねえよ」
「ごめん、やっぱり初陣だったからちょっと心配だったんだ。でもこれだけ動くことが出来るなら、大丈夫かな。どこかおかしいところはない?」
安堵しながらもどこかまだ心配げな雰囲気のある堀川が、和泉守の上から下までを眺めながら問い掛けてきたのに合わせて、和泉守もざっと自身の状態を確認する。敵からの攻撃を受ける前に倒したので怪我はなく、初陣だからといって無茶に動いたわけでもない。大丈夫だと応えようとして堀川の目が肩に止まったことに気づくと、その問いの意味を理解した。理解して、応えの言葉とは別の言葉を口にする。
「お前オレをなんだと思ってるんだ。オレは和泉守兼定だ。だんだらがあってもなくても、オレはオレだ」
浅葱色のだんだらは誇りだ。そしてそれは和泉守兼定を和泉守兼定たらしめる物でもある。けれどそれは一つの要素に過ぎず、それが欠けていたとしても、己は己だ。
それを今、証明してみせた。練度の高い堀川たちからしてみれば弱い敵であったかもしれないが、初陣にして一人で敵を倒し、こうして無傷で立っている。それは堀川たちの懸念に対する何よりの答えではないか。
「ほうじゃな」
同意するように明るい声が聞こえてくる。振り向けば戦が始まる前の真剣な顔つきではなく、へらりとした、けれどどこかまだ固い笑みを浮かべた陸奥守が立っていた。
「おんしは確かに、和泉守兼定じゃ。初陣でこがぁに動けるとは、流石じゃのお」
肯定されて、ふと胸が楽になる。意識せずとも、身体の力が抜けていく。その感覚に、どこか己でもだんだらの外套がないことを意識し、変に気負っていたのだと気づいた。証明してやると言って、期待をしていると言われた。それが知らぬ間に己を絡めとり、己の言葉が己への圧力となっていたようだ。
ひたりと合わせられた視線の先で、陸奥守の琥珀の目がゆると優しく溶ける。
「やっぱりおんしは強い」
陸奥守に柔らかく笑まれ、じわじわと胸の裡に温かさが広がる。急に気恥ずかしくなり、その顔を見ていられなくて視線を逸らした。逸らされた視線にきょとりとした気配が伝わってきたが、陸奥守は何を言うこともなく大きく息を吐く。もしかしたら陸奥守も堀川と同じでだんだらがないことの影響がどのように現れるか不安だったのだろうと、確証もないがそう思った。