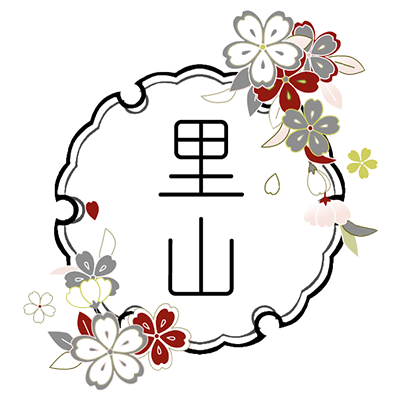発行物紹介
introduction
いずむつ
青に揺蕩い、赤に消え 中
とある本丸の、だんだらを欠いて顕現した和泉守と陸奥守の記録。
告白をして振られた(?)和泉守は、手合わせで一本取ったら、というチャンスを与えられ、以降勝負を挑むも負け続けていた。
その頃本丸では、二週間以上雨が降り続け、違う遠征先に出てしまうという不具合が続いていた。
不具合の調査に入った政府の立ち会いのもとで行った遠征の遡行が失敗する。出た場所は、どの時代でもなく、他の本丸だった。
そこから、陸奥守の様子がおかしくなる。
続き物の中巻。
いずむつ要素は薄いです。でも、いずむつです。
※オリジナル本丸捏造設定多々あり。
※オリジナル男審神者がかなりしゃべります。名前はありません。1P目・2P目くらいの絡みです。
※敵の流血表現あり。
※土佐弁等作中方言はコンバータに頼っています。
イベント頒布価格1000円
A5 / 114P
2016年5月4日発行
現在頒布中
青に揺蕩い、赤に消え 中 サンプル
SAMPLE
本丸の一角にある道場に、硬い木で打ち合う音が響く。かん、かん、と調子よく響いていた音は徐々に早くなり、打ち合う音だけでなく板張りの床を強く踏む音も混じり始める。一際強く床を踏む音がして、間をおかず激しく打ち合う音が聞こえた後、からん、と小さな硬い音が響いたのを最後に、それまでの激しさが嘘のように静かになった。
打ち合いの音の代わりに、しんと静まり返った道場内には、はぁ、はぁ、と荒い息が響く。
「あー!」
床に背をつけた和泉守は、己の頭の横に木刀の先を突いて覆い被さっている打ち合いの相手を見あげた。悔しさと苛立ちを滲ませたその視線を受けて、相手がにやりと口角を上げる。
「わしの勝ちじゃ」
「くっそ」
思わず漏れてしまった声に、陸奥守が声をあげて笑いながら木刀を引き上げ、身体を和泉守の上から退けた。軽く拘束されていた空間がなくなり、和泉守は深く息をする。
息を整えながら、打ち合いの最後に弾かれた木刀を目で探せば、かなり遠くまで飛ばされていた。取りに行かねばならないが、一度背をつけてしまったために起き上がれそうにもない。どうせもうこれで打ち合いも終わりだと、後で取りに行くことにして、今は息を整えることだけに集中する。ひんやりとした板間が、火照った身体にちょうどいい。
陸奥守も同じように疲れたのか、道場の床に寝転がる和泉守の隣に腰を下ろす。胡座をかき、胸を反らすように手を後ろについて、大きく深呼吸を繰り返す。頬や顎を汗が伝っていく様を見ながら、こうして道場で寝転がったまま陸奥守を見るのは何度目だと記憶を辿った。
「くそ、なんで一本取れねえんだ」
荒い息の中、悔しさに呟いた言葉を拾った陸奥守が顔をゆっくりとこちらへ向ける。
「練度ももうそんなに差がねえ、実戦だって積んできた。他のやつらからならどうにか一本取れるってのに、お前からだけは取れねえ」
和泉守が特付きになってから約三ヶ月が経ち、その間和泉守は練度を大きく上げた。数値で表せば、陸奥守に振られてから、否、陸奥守と初めて行った手合わせで負けてから、既に二十以上も練度を上げている。だというのに、未だに陸奥守に手合わせで勝つことはできていない。今日も、負けた。
二人の間で一つ練度が上がるごとに真剣な手合わせをする、という約束をしてから二十回近く手合わせを行っている。けれど和泉守の練度が上がるに合わせて陸奥守も練度を上げていくために、陸奥守との練度の差は縮まっても練度を超えることはなかった。
だが、練度が違えども他の刀剣たちからは一本を取れる時があるというのに、陸奥守にだけは勝てた試しがない。いくら踏み込んでもいなされ、薙いだ刀身は弾かれる。これが実戦ならばどんな手を使ってでも一本を取りに行くが、あいにくとただの手合わせであるために実戦戦法は使うことができなかった。
一向に取ることの出来ない一本に、焦れて疲れも見えてくる。なんでだ、となかなか一本を取れないもどかしさに、ずっと心の中にあった疑問を問いかければ、陸奥守は小さく笑う。
「おんしも懲りんのぉ」
「あったりまえだろ。お前から一本取るまで諦めてたまるか」
特付きになったその時、初めて陸奥守と一戦を交えた。その時に「守りたい」と告白めいたことを告げ、拒否されて、けれど手合わせで一本取れるようになったら、ともう一度機会を与えられた。手合わせをして陸奥守から一本を取れば、和泉守の想いを受け入れると陸奥守は言った。だから、和泉守は陸奥守から一本を取ることに必死になっている。一本をとった先の約束の実現よりも、一本を取ることが目標になっているのにも気づいてはいるが、まずは勝たなければ先にも進めないのだ。
だから諦めてなるものかと強く陸奥守を見つめると、やれやれとでも言いたげに細く息を吐き出した後、陸奥守が反らしていた上体を起こす。
「お前も、本丸にいる方がいいって言っときながら、オレが特付きなった途端に出陣回数増やしやがって。オレに負けるのが怖いんだろ」
「ほがなことはないぜよ。審神者から短刀らぁの育成もしたい言われちゅう。やき、ちっくと出陣が増えただけじゃ」
陸奥守の出陣の回数は、和泉守が顕現した頃よりも明らかに増えている。確かに最近は色々と落ち着いてきて、和泉守以降に顕現したものや短刀たちの練度が低いものの育成も増えてきた。教育係と自他共に称する陸奥守が引率としてついていくのは自然なことだ。けれど、和泉守にはそれがどうにも気になっていた。
戦に出るよりも本丸にいる方がいいと言った、いつかの言葉もまた陸奥守の本心であることには間違いだろう。だというのに、例え短刀たちの補助的な意味合いが強いとはいえども戦場に出る回数が増えたのは、何か別の思惑があるのではないかと思わずにはいられない。
探るように起き上がった陸奥守を眺めていると、その和泉守の心中を見透かした上で笑い飛ばすように、はっはっは、と大きな声が道場内に響き渡る。
「おんしはすんぐわしを抜くき、そがぁに心配せんでもえいがよ」
「それはそれでなんかむかつくな」
己の成長速度が早いということを言われているのは判るが、まるで陸奥守が己に抜かされるために練度を調整しているようにも聞こえてしまい、僅かばかりの的外れな苛立ちを感じたままに呟く。ぶは、と盛大に漏れた息にまた笑い飛ばされるのかと思ったが、視線を向けた先にあったのは意地の悪い笑みだった。
「練度と勝負の勝ち負けは関係ないきに」
「オレに練度抜かされても勝てるって? 随分な自信じゃねえか」
この三ヶ月、ただ練度を上げるだけではなく、他の刀との手合わせや自主鍛錬も行ってきた。練度と同じように、腕も磨いてきたつもりだ。けれど陸奥守は、それでも己に勝てるというように笑う。
「勝てる自信らぁてないぜよ。けんど、おんしには負けん」
「なんでそんな言い切れるんだ」
「知りたいがか?」
視線で教えろと返せば、ほいたら教えちゃお、と少しばかり得意げな声が返ってくる。
「おんしゃあ、興奮すると真正面からしか突っ込んでこんろう。やき、予測が簡単になる。敵さんにゃあおんしが真正面から突っ込もうが邪道剣法使おうが関係ないけんど、わしから一本取ろう思っちょるんなら、直さんと取れんぜよ」
陸奥守の口からでる己の悪癖に、和泉守は驚きに目を僅かに見開いた。堀川や他のものたちと手合わせをした時に指摘された所はなるべく直してきたのだが、そのような癖があることは知らなかった。だが、それを教えていいのだろうか。弱点を教えるということは、つまりその弱点を克服することが出来たのならば、一本取ることが出来るということだ。
「敵に塩を送っていのかよ」
「おんしは敵じゃあないろう」
にひひ、と笑う陸奥守は楽しそうだ。
「おんしが気づくがを待っちょったけんど、おんしゃあ全然気づかんき」
「自分の癖なんか、誰かに教えてもらわねえと気づくわけないだろ」
「ほれ、そういう他人に教えてもらおうと思っちゅうがが駄目なんじゃ。試行錯誤していかんと」
「へーへー」
説教じみてきた言葉を遮るようにして、和泉守は身体を起こした。まだ疲れは取れていないが、息はだいぶ落ち着いてきて、動くことは出来る。落ち着けば身体中にじわりとまとわりつく汗が気になって、さっさと流してしまいたいと思いながら、服で乱雑に汗を拭う。
「けんど、おんしは強うなった」
汗を拭う手を止めて、陸奥守を見る。目が合えば、陸奥守が頬を緩めた。和泉守の成長を喜んでいるような、楽しんでいるようなそんな笑みに、心の臓が小さく脈打った。急に気恥ずかしさを覚え、それを振り払うように敢えて言葉を強くする。
「見てろよ、次はぜってー一本取ってやる」
「その台詞、何度目かのぉ」
「次こそ絶対にだ」
からからと笑う陸奥守を睨めつけると、和泉守は立ち上がる。続いて陸奥守も立ち上がり、伸びをした。