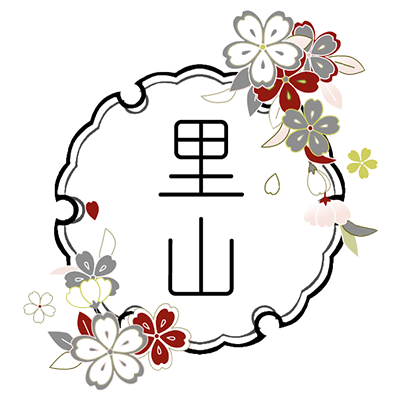発行物紹介
introduction
みかつる
成人向
むかしがたり
「にいさまと、呼んでくれないか?」
平安時代、三条の屋敷にいた頃に三日月が鶴丸に願った呼び方から始まる、なれそめほのぼの話。
全体的に可愛い感じを目指しました。
捏造過多。雛鶴注意。陸奥守初期刀本丸です。
初みかつる本です!
いろいろとおかしな所があるかもしれませんがご容赦ください。
カバーは「もめん。」の大森ソイ様(Pixiv)に作っていただきました
イベント頒布価格900円
文庫・フルカラーカバー / 144P
2016年7月3日発行
頒布終了しました
むかしがたり サンプル
SAMPLE
「みかづきさま!」
三条の屋敷でくつろいでいる時、遠くからとたとたと軽い足音と、それに続いて己を呼ぶ声が聞こえた。声のした方へと顔を向けると同時、白いものが目の前に飛び込んできた。
「みかづきさま、見つけた!」
たどたどしく発された己の名に、三日月は不思議な心地がした。他人行儀のような呼び名は、実際に他人であるから仕方のないことではあるが、けれど僅か寂しくもある。己が内に芽生えたその感情に驚きつつも、応えのない己を訝しげに見上げる童子に笑いかけた。
「ああ、いやなんでもない。突然現れたからな、少々驚いたのだ」
「驚いた? 驚いたのか!」
ぱぁと突然明るくなった童子の表情に、頬が緩む。驚いたと繰り返し言いながら狩衣へと飛びついてくる童子を受け止め、その柔らかな髪を撫でた。
「今日は、みかづきさま一人なのか?」
「ああ」
「じゃあ今日は、おれがみかづきさまを、ひとりじめだな!」
望月のような目を更に丸くして顔を輝かせる童子は、己を独り占めできることが嬉しいと全身で伝えてくる。その様子に目を細めながら、三日月は小さな身体を抱き上げた。
「俺も、今日は鶴を独り占めだな」
いつもは三条の兄弟がいるのだが、今日はたまたま誰もいない。みな刀の付喪神ではあるが、名刀匠と名高い父に打たれた刀は、父が出向く場所や家の周辺であれば出かけることが可能だ。今日は皆、それぞれ思うままに出かけている。
抱き上げられ落ちないように首に縋り付いてきた童子は、三条の兄弟にもよく懐き、遊んでもらっていた。父の弟子が打った刀の付喪神であり、いわば年の離れた兄弟にも近しい童子を、三条の兄弟は皆、好ましく思っている。鶴と仮に名づけられた童子は未だ小さく、僅かばかり身体より大きな白い衣装に身を包んで、よくこの庭を駆け回っていた。その鶴丸の姿を眺めるのを、三日月は好んでいた。
「みかづきさま、みかづきさま、今日はなにしてあそぶんだ?」
ああ、そうかと三日月は思う。こんなにも懐いてくれ、そして兄弟のように好ましく思うものだからこそ、敬称のついた名で呼ばれることを寂しく思うのだ。ふむ、としばし考える。
「鶴」
「ん?」
あれもしたい、これもしたい、と指折り思案していた鶴丸は、呼ばれた名にくるりと振り返る。間近にある望月の目は、三日月と遊べることへの期待と歓喜からか、きらきらと輝いていた。
「一つ、頼みがあるのだが。にいさまと、呼んでくれないか?」
「にいさま?」
「そうだ。父こそ違えど、俺とお前はもう兄弟のようなものだ」
「きょうだい」
おうむ返しに呟く鶴はぱちぱちと数度瞬きをしてから、一度口を開きかけるもすぐに閉じてもごもごする。
「でも、国永が」
言い淀む鶴の気持ちも判らなくはない。父が師と仰ぐ者が作り上げた刀なのだ、馴れ馴れしく呼ぶことはおいそれとできないだろう。だから、三日月はゆっくりとその滑らかな頬を撫でる。
「俺がそう呼んで欲しいのだ、鶴」
できるだけ柔らかく笑いかければ、またも瞬きをした鶴は、み、と言葉を紡ぐ。
「みかづき、にいさま?」
こてり、と小首を傾げて呼ばれた名に、胸の辺りが温かくなる。自然とゆるむ頬を、止めることはできなかった。こうも感情を揺り動かされるとは。
「みかづきさ……にいさま、どうしたんだ」
一人で笑う三日月を不思議がった鶴が、手を伸ばして頬に触れてくる。その小さな温かさにまた笑って、三日月は腕の中に収まる鶴の頭を撫でた。
「よきかなよきかな」
「ああ。あったな、そんなこと」
三日月がふと懐かしい昔語りをしてみれば、隣にいた鶴丸がそっけなく言う。縁側に並んで座り、主から貰ったという栗ようかんを前に手ずからいれたお茶をすする鶴丸は、白い身体と白い衣装はそのままに、もうこの腕には収まらないほど大きく成長していた。
歴史修正主義者による歴史改変を阻止すべく呼び出され、再会してから僅か。積もる話は多く、こうして時間を見つけては鶴丸と茶を共にしている。
これまでは互いに辿った歴史を語ることも多かったが、今日はふと、昔日に鶴丸から兄様と呼ばれていたことを思い出して昔語りをしてみた。だが、どうにも鶴丸の反応は鈍い。栗ようかんを菓子用のようじである黒文字で切り分けながら、鶴丸が問う。
「なんで急にそんな話をしたんだ?」
「なに、左文字兄弟を見ていてな。ふと思い出したのだ」
「ああ、あそこは仲いいよな」
兄様、と柿を持って江雪の元へ向かう小夜と、その後ろを見守るようについていく宗三の姿は微笑ましいものがあった。それに呼び起こされたのは懐かしい光景で、同時にその時の温かな気持ちまで思い起こされた。
「鶴」
「ん?」
栗ようかんを咀嚼しながら、呼ばれた鶴丸がぱちりと瞬きをする。そんな動作は昔日と変わらないというのに、三日月へ接する態度は昔日よりも他人行儀だ。三日月だけではなく他の刀にもその態度であるので、それは成長したからであろうと受け入れていた。
だが、偶に思い出す昔日の懐かしさに、僅か寂しくなるのも事実だ。過ぎ去りし時に残した心を羨むなど爺になった証拠よ、と胸中で自嘲する。
「三日月?」
名を呼んだきり黙ってしまった三日月にぼけたかと笑う鶴丸は、次の栗ようかんに黒文字を刺し持ち上げた。その笑みは、昔によく見ていた笑顔とさほど変わらず、だから三日月は自然と口を開いていた。
「もう、にいさまと呼んではくれぬか?」
ぴたり、と鶴丸の動きが止まる。栗ようかんを食べようと開いた口をそのままに、視線だけを寄越した。器用だなと感心していると、鶴丸は栗ようかんを皿に戻し、いやいやと呟く。
「まぁ確かにいっときそう呼んでたことはあったが……もう昔のことだ。俺はもう童子じゃないし、君と俺はとうにそんな間柄じゃないだろ」
「なにも変わってないだろう?」
鶴丸が鶴丸であることも、己が三日月宗近であることも、鶴丸の笑みも言葉も、あの頃より何も変わっていない。三日月には、主や姿形こそ変われども昔日と変わったことなどないように見えるが、鶴丸はそうではないらしい。手首をぱたぱたと軽く振って、否定する。
「あの時は国永がいたし、兄弟のように迎え入れてもらっていたから違和感もなかったが、今は国永もいないし一旦違う主の手に渡ったんだ、もうただの他人だ」
「寂しいことを言ってくれるなぁ」
他人などと。
態とらしく袖で口元を覆ってみせるが、鶴丸は気にした様子もなく栗ようかんを口に運ぶ。
「昔の鶴はにいさまにいさまと寄ってきて、可愛かったというのに」
「年をとると現実も見えなくなるのか?」
「ふむ、老眼、というやつかな? そのようなことがこの身に起こりうるのか、後で主にも聞いておこう」
そう言った三日月に、何が面白いのか鶴丸はくつくつと喉を鳴らして笑った。
このような軽口を叩いてくれるほど気安い位置に己はいるのだと思うも、鶴丸にしてみればそれは特別なものではなく、他の刀や、はては主にまでこの調子である。昔日はただ一人、三日月だけをにいさまと呼び後をついて回っていたというのに。
「鶴丸」
「何度言われたって、言わないからな」
「どうしても駄目か?」
そこまですげなく断られては、少しばかり意地にもなるものである。
断れない、と他の刀達によく言われる顔をして鶴丸に乞うが、鶴丸はその顔にも動じることは無い。一瞬言葉に詰まったようだが、それでもその首が縦に振られることはなかった。
「爺がそんな顔をしても無駄だぜ。そんなに言ってもらいたいなら、短刀達に頼めばいいじゃないか」
「そうではない」
短刀達に言ってもらっても意味が無い。ふるりと頭を横に振って否定する。
「そうか、鶴は俺のことが嫌いか」
「何でそこに思考が飛ぶんだ」
そんなことを言われても言わないからな、と念を押す呆れた声に、こうも頑なでは仕方あるまいと、三日月はため息を吐く代わりに茶を飲む。随分と温くなった茶と共に、諦めを飲みこんだ。
こうなってしまえば、鶴丸は意地でも言わないだろうという事は判っている。引き際は弁えているつもりであるし、なにも今すぐでなくとも時間はある。懐古する昔に感情を呼び起こされた時にでもまた、強請ってみようか。
ちらりと隣を見れば、栗ようかんを全て食べ終えた鶴丸が、同じように茶をすすっている。にいさま、と呼ぶ今より高く幼い声が耳に聞こえる気がした。久々に聞いてみたかったのだがと、懐かしさに疼く胸に薄く笑みを浮かべ、独りごちる。
「三日月。君はこれが嫌いだったか?」
ふと鶴丸が声を上げる。これ、と鶴丸の視線が指すのは、二人の間にある盆の上に置いたままだった栗ようかんだ。手付かずで残っていた三日月の分の栗ようかんに、鶴丸は僅か首を傾げる。
「なに、少し話すのに気を取られていてな。欲しければ食べていいぞ」
じぃと栗ようかんを見つめる視線が物欲しそうに見えてそう言えば、いいのか、と、年に似合わずはしゃぐ声がする。首肯した三日月に礼を言って、鶴丸は嬉しそうに栗ようかんの皿をとった。
そういえばこの栗ようかんは鶴丸が所望したものであったと思い出し、美しく育った身の内に変わらぬ幼子を見つけた気がして、三日月は微笑む。
「童子ではないと言いながら、まるで童子だな」
「この栗ようかんが美味いのがいけないんだ」
「幼子の理由だな、それは」
ははは、と笑えば、栗ようかんを口に運んでいた鶴丸が、むすりとした表情を浮かべる。それもまた、昔日に共にいた時を思い出させた。他のもの達がいる時にはあまり見せぬ幼い仕草に、温かなものが胸に広がっていく。
「まぁ」
鶴丸がぽつりと呟く。
「君の前だからな。三日月にいさま」
何を言われたか一瞬理解できなかったが、兄様と呼ばれた名に、三日月は動きを止め、瞬きを一つする。よほど呆けた顔だったのだろう、三日月の顔を見た鶴丸が、ぷ、と吹き出した。
「ははっ! 驚いて声も出ないか?」
悪戯が成功した時のような、してやったりという軽やかな声に、漸く思考が戻ってくる。
「おお。あまりに驚きすぎて、聞いていなかった。鶴、もう一度呼んでくれぬか」
「それは残念だったな。一度きりの特別大盤振る舞いだったというのに」
からからと笑った鶴丸は、残りの栗ようかんを一口で食べ、空になった皿と盆を持つと立ち上がった。
「どうした?」
「いや、光忠に呼ばれていたことを思い出したんだ。ついでだ、これは片付けておくぜ」
この場を離れようとする嘘だと、三日月でなくとも判る。鶴丸にしては、あまりに粗雑な嘘だった。
「鶴」
背を向けた鶴丸に呼びかければ、肩越しに視線だけが返る。視線が交わった瞬間、鶴丸は決まりが悪そうな表情をするがそれはすぐに消え、平時と変わらぬ、からかうような笑みが浮かぶ。
「じゃあまた後でな、にいさま」
言って、鶴丸は手を振りながら素早くその場を後にする。その後ろ姿を呆と見送った三日月は、白い服が角を曲がり消えたと同時に、笑い声を息に乗せた。
「二度目はないと言うたのになぁ」
鶴丸の言う驚きを得るためにからかわれたとしても、二度も呼んでくれた鶴丸は存外己に甘いらしい。それが嬉しくて、自然と浮かぶ笑みを抑えることなど出来なかった。
にいさま、と呼んだ鶴丸の声を反芻する。昔日よりも声音は低くなっているが含まれる甘さは同じで、三日月の胸を温かくしていく。
「愛い子よ」
去り際に見た鶴丸の赤に染まった耳を思い出して、三日月はぽつりと呟いた。
「よきかな、よきかな」