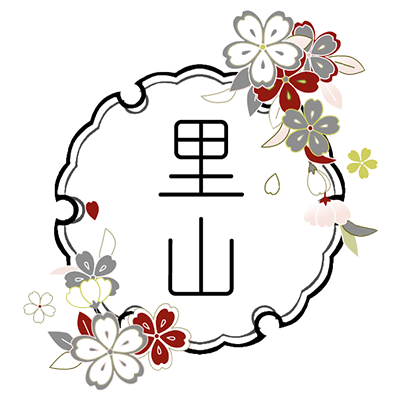むかしがたり サンプル
SAMPLE
はぁ、と息を吐いて、鶴丸は近くの柱にもたれかかる。
三日月が顕現して二週間ほどしてから、にいさまと呼んでくれないかと言われた。それから一ヶ月と少し。三日月は未だに事あるごとににいさまと呼ぶように言い、鶴丸も三日月を驚かすときや不意をつく時などに口にしている。だから、鶴、と呼ばれて、にいさま、と返す癖のようなものが、知らず、ついていたらしい。
「それがあそこで出るなんてなぁ」
完全に油断した。陸奥守と燭台切は同じ第一部隊に所属し、最近までほとんど毎日共に出陣をしていたのだ。多少なりとも気の緩みはあったかもしれないが、よりによって、だ。
そもそもいつの間にそんな癖がついていたのか。他の刀剣の前でうっかり呼んでないだろうか。もし大倶利伽羅あたりに聞かれていたら死ねる自信がある。
明日も、第一部隊で出陣の予定がある。ぐぬぬと呻きながら、どうやって誤魔化そうかと思っていると、背後から慣れた気配が近づいてくる。
「鶴。今日はここで食べるのか」
背後を伺うと、穏やかな笑みを浮かべた三日月が立っていた。手にはだんごが乗った盆がある。いつものゆっくりとした歩みで鶴丸の側まで近づいてくると、側に盆を置いて縁側に座った。ここには三日月がいつも座っている座布団はないため、足は外へと垂らしているようだ。
「おお、ここからの眺めもなかなかに良いな」
鶴丸の胸中など知らず、のほほんとした声で三日月は縁側から見える庭を見回す。そうしてひとしきり景色を堪能した後、くるりと後を振り向いた。
「鶴丸。おやつは食べぬのか? 食べぬのなら俺が食べてしまうが」
おいでと言うように、三日月が自身の隣をぽんぽんと叩く。先ほどのこともあって三日月の側にはあまり寄りたくはないが、審神者が買ってくるだんごは非常に美味しく、捨てがたい。結局三日月の催促とだんごに負け、鶴丸は大人しく三日月の隣へと腰掛ける。
そら、と差し出されたお茶を受け取り一口飲み、三色だんごを一つかじる。だんごはもちもちとしていて、やはり美味しかった。
「うむ、美味いな」
三日月も餡だんごを頬張り、頬を緩ませる。その笑顔を見ていると、何か小言を言う気も失せてきた。明日のことは明日考えればいい、まぁあの二人ならば言いふらされることもないだろう。そう考えを改めて、漸く気分が落ち着いてきた。
「先ほどはどうしたのだ」
だというのに、蒸し返すのは当事者でもある三日月だ。鶴丸は行儀が悪いと思いながらも、一つだんごを抜き取った串を三日月へと向けた。
「君がそれを言うか?」
「はて、なんのことか」
本当に判らないのか、三日月はもちもちとだんごを咀嚼しながら首を傾げる。
「幼い頃の呼び名で呼んだところを、他のものに見られたんだ。恥ずかしくもなるだろう」
何も言わず思わず逃げ出したのは失敗だったとは思うが、今の己しか知らないこの本丸のものたちの前で、まだ己というものが形成されていない頃のことを僅かでもにおわせてしまった。それが例え「にいさま」という呼び名だけだとしても、鶴丸にとっては恥ずかしいものなのだが、三日月はそれが判らないとでも言うような顔をする。
「恥ずかしいだろ。童子の頃のことを知られるなんて」
「俺は恥ずかしくないぞ?」
「君にとってはそうでも、俺にとっては恥ずかしいことだ」
「そうか、それはすまなんだ」
「……いや、判ってくれればそれでいいんだ」
三日月のせいだと言うのは、八つ当たりにも近い。三日月があの場で特に何かをした様子はなく、強いて言えば癖を付けられたくらいだ。それを本人も判っているだろうに、自分の過失にするところは昔から変わっていない。
いつものように鷹揚に笑う三日月に、ふぅと肩の力を抜く。完全に毒気を抜かれて、鶴丸は二つ残っただんごを横から口で挟み、串を引き抜く。器用に二つのだんごを口の中へと入れながら、だが、と呟いた三日月を見た。
「だが、あのものたちならば、俺と賭けをして負けたとでも言えば納得してくれそうだが」
「賭けか。なるほど、それはいいな」
陸奥守と燭台切相手に誤魔化すも何もないが、どちらかと言えば己の羞恥心を納得させるためのものだ。あの二人は己が三日月のことをにいさまと呼んだとしても、そんな関係だったのかくらいにしか思わないだろう。
「実際に賭けでもしてみるか?」
「へぇ、何でやるつもりだい?」
「ふむ……。そうだな、今日は誰が誉を多く取って帰ってくるか、とかはどうだ?」
「それは賭けにならないぜ、三日月。今日の出陣部隊の面々を忘れたか?」
言えば、三日月が空を見上げて考え始める。今日の出陣部隊は、短刀たち五振りに加え、岩融だ。最近練度が上がってきた岩融は、その一撃で複数の敵を屠るまでになっている。最近は出陣すれば誉を取ってくるようになり、その時共に出陣していた今剣にずるいですよと怒られていた。それらを考えると、今日の出陣で誰が多く誉を取るかなど、火を見るより明らかだ。
「判らぬぞ? 今日は岩融よりも練度の高い乱や愛染、五虎退もいる。勝負とは終わってみるまで何が起こるか判らぬものだ。だから、驚きがあるのだろう?」
人の台詞を使って、まるで鶴丸を挑発するかのように口元に弧を描いた三日月に、ならば乗ってやろうと鶴丸も口角を上げた。
「安全牌である岩融では、勝負にならないというわけか。君がそのようなことを言うとは思わなかったぜ」
「ははは。爺もたまには勝負に出ねば、なまってしまうからな」
何がなまるのかと聞けばはぐらかされてしまい、それで、と逆に誰に賭けるのかを問われる。
「そうだな……練度だけで言えば今日の編成の中では五虎退が一番上だが、どうにも踏み込みが弱いところがある。愛染もだな。後は乱と薬研、秋田か……」
今日の出陣部隊の面々を脳裏に浮かべ、以前に共に出陣した時のことや鍛錬の時の様子を思い出す。岩融よりも先に動き誉を取りそうな刀は誰か。暫し考えて、よし、と膝を叩いた。
「俺は乱に賭けるぜ」
「ほう」
「各能力の釣り合いが取れてきている。最近は機動も踏み込みも安定してきているし、練度も上がって攻撃力もついてきたからな」
「なるほどなるほど。ならばそうだな、俺は愛染に賭けてみようか」
安全牌では面白く無いと言ったわりには、三日月は、岩融以外では一番誉を取る可能性が高いところを選んだ。勝負に出ると言っていたが、これが三日月の勝負なのだろうか。けれど審神者の方針で短刀たちの練度は足並みが揃っており、誰にしたところで確率は同じなのかもしれない。
「じゃあ、賭けの内容はどうする? なんのひねりもないが、勝った方の言うことをきく、でいくか?」
「ああ、そうだな。それならば、お前に兄と呼ばせていたという言い訳もできるだろう」
自身が勝つことを微塵も疑っていない三日月は、だんごを頬張りながらにこりと笑う。その自信は何処から来るのかは判らないが、己も己の判断には自信がある。
「そんなことをしてもらわなくとも大丈夫だ」
「そうかそうか」
頷く三日月を横目で見ながら、鶴丸は餡だんごを手にとった。出陣している部隊が帰ってくるのは、確か四時過ぎだと聞いている。先ほど台所で見た時間とそこから経過した時間を考えると、出陣部隊が帰ってくるのは後もう少しだ。おやつを食べながら話をしていればあっという間に時間が過ぎるだろう。
「先程まで恥ずかしいと呻いていたと思ったが、俺の気遣いはいらぬか」
「うぐ」
餡だんごにかじりついた瞬間を見計らったかのように呟かれた一言に、ひと欠片を喉に詰まらせかけて咳き込む。どんどんと胸を叩き、差し出されたお茶を飲み干して、詰まっていただんごが胃に落ちて呼吸が楽になってから、じとりと横を睨んだ。少し涙目になっているのはご愛嬌だ。
「おお、すまぬな。少々間が悪かったようだ」
詫びにこれをやろう、と、三日月が手をつけていない三色だんごを鶴丸の皿に置く。そんな物で誤魔化されるかと思いつつも、審神者がこのだんごを買ってくるのは極稀で、なかなか食べられない物だ。
「仕方がない、今日はこのだんごで誤魔化されてやろう」
「ああ、そうしてくれ」
台所で盆を押し付けた時に燭台切に頼んだのか、ちゃっかりと持ってきていた急須からお替わりの茶を注いだ三日月は、温かい茶を一口飲んで、ふ、と息を吐きだした。
「しかし、懐かしいな」
三日月がぽつりと呟いた言葉に、最近はそればかりだな、と首を傾げた鶴丸を、懐かしそうに細められた目が捉えた。
「今泣いた烏がもう笑っているだろう。それが、懐かしくてな」
「おいおい。それは童子に使う言葉だろう。俺に使うような言葉じゃない」
「そうかそうか、そうだったな。あいすまぬ」
「君なぁ」
本気で謝ってはないのだろう、はっはっはと笑い声を上げる三日月に呆れてみせれば、もう一度すまぬなと謝られた。
「なに、お前を見ているとどうにもあの頃が思い出されてな」
「昔ばかりでなくちゃんと今を見てくれよ」
見つめられる視線に乗るのは郷愁で、その視線を受けているとあの頃に戻ったような気になってしまう。その空気は心地よいものだが、同時に温かいような熱いような感情が、胸の奥をちりちりと焦がす。覚えのあるようなないような感情に、身の裡がざわめくのだ。
「見ているとも。あの頃も、拗ねたと思えば機嫌が良くなり、機嫌がいいと思えばすぐに怒ったりしていたな」
「……あの頃は、仕方がないだろう。まだ意思が形成されて間もなかった頃なんだ」
「今も変わらぬ」
鶴と名を呼びながら、三日月が頭を撫でる。それは昔に良くしてもらったような優しい撫で方で、この本丸に来てからは初めてのことだ。何かの感情が熱く焦がしていた胸の奥が、ほわりと温かくなる。
「やめてくれ、俺はもう童子じゃないんだ」
「何を言う。俺にとっては昔も今も、鶴は可愛い童子だ」
「毎度毎度、立派に成長した俺を捕まえて童子とは言うねぇ、にいさま」
童子と言われて、ならばからかってやろうと呼び名を口にした瞬間、ぎしりと縁側の板が鳴る音がした。鶴丸はぎくりと身体を強張らせて、音のした方を見る。誰にも聞かれてませんようにという願いは、儚く砕け散った。
「……大倶利伽羅」
呼ばれたから立ち止まったというように足を止めた大倶利伽羅は、顔をひきつらせて座る鶴丸を見下ろす。
「……聞いたか」
「人の話に聞き耳を立てるようなことはしない」
「そうか。じゃあ質問を変えよう。聞こえたか」
「聞かれたくないのなら、こんなところで話すな」
それはつまり、聞かれたということだ。最もなことを言って、大倶利伽羅は何事もなかったかのように去っていく。その背が角を回ったところで、またやってしまった、と鶴丸は項垂れた。
「よいではないか。あやつはそう言いふらすことはしまい」
「そうじゃなくてだな」
この本丸で鶴丸は顕現するのが早かった。太刀の中では二番目に顕現し、全刀種の中でも六振り目に顕現をした。だから、どちらかと言えば今まで鶴丸は、本丸の刀たちの兄的な気持ちでいたのだ。
実際にそうだとは思われていなくても、年長者として振舞ってきたことも多い。大倶利伽羅だけではなく、燭台切も陸奥守に対してもそうだ。特に大倶利伽羅は同じ伊達家にいたという繋がりがあり、何かと兄のように世話を焼いてきたのだが、その大倶利伽羅に聞かれてしまったことは、ここ数日で一番の失態だ。
明日から敬ってもらえなかったらどうしようかと鶴丸は考える。敬われてはいないかもしれないが年長者だからと頼ってはくれている筈で、明日からそれすらも無くなったらどうしようか。
「君の前だと、どうにもあの頃に戻ったような気持ちになる。それがな」
三日月と二振りだけならばいい。だが、鶴丸にとっては、にいさまと呼ぶのは小さいころの己であり、今ここにいる鶴丸国永ではないのだ。だから、兄として、年長者として振舞っていたものの前で、にいさまと呼んだところを見られたのが、恥ずかしい。
言い訳が必要だろうか。けれど大倶利伽羅も己と三日月が旧知の仲であることは知っているはずで、ならば余計な言葉は要らないかもしれない。だが、己が言い訳をしたい。
ぐるぐると考えていると、三日月が湯のみを置く小さな音が耳に届く。
「鶴は、俺をにいさまと呼びたくないのだな」
ぱっと顔をあげる。呟きが、どこか寂しそうに聞こえたのだ。
「いや、そんなことは」
「だが、そのように頭を抱えるということは、そうなのだろう」
それを、否定は出来なかった。にいさまと呼ぶことが嫌なわけではない。恥ずかしいだけだ。けれど、否定出来ない行動をした自覚もある。しまったと、腹の奥の熱が引いていく感覚に思う。
「ははは、よいよい。俺はそう気にしてはおらぬよ」
声も顔も、平時と変わらない。けれど、その横顔にはどこか寂寥さが感じられ、鶴丸は、にいさま、と呼びかけた。だがその声は、出陣部隊の帰城を告げる音にかき消される。
「どうやら戻ってきたようだな」
遠く、遡行用の門がある方向を見る三日月につられて、鶴丸もそちらを見た。ここからでは庭の木々が邪魔をして部隊の姿は見えないが、慌ただしい足音は聞こえてこないので重傷者はいないだろう。
「さて、賭けはどうだろうか」
姿も見えなければ声も聞こえないこの位置では、誰が誉を取ったのかは判らない。三日月は動く気配もなく、なんとなく鶴丸も動きづらい。誰かが通りがかるのを待っていればいいかと、ずっと手に持ったままでいて、奇跡的に垂れることのなかった餡だんごを齧る。
少ししてぱたぱたと聞こえてきた足音に振り返れば、陸奥守が向こうからやってくるのが見えた。
「おーい、陸奥守」
手を振って呼べば、気づいた陸奥守が立ち止まる。
「なんじゃあ。鶴さんらぁ、こがなとこでおやつかえ」
「ああ。まぁいろいろあってな。これから審神者のところに報告に行くんだろ?」
「おん、出陣しよった部隊がもんてきたき、報せにの」
近侍である陸奥守は、部隊を出迎えて審神者に帰城の報告をするという任がある。誰が誉を取ったか、誰が負傷したか、それらの簡易報告も、近侍の役目だ。
「今帰ってきた部隊、岩融たちの部隊だろ? 誰が誉を多く取ったんだ?」
「今日は愛染じゃな。三つも誉を取った言うて、自慢してきよった。けんど、そがぁなこと聞いてどういたんじゃ」
「いやなに、短刀が頑張ったのなら菓子でもやろうかと思ってな。引き止めて悪かったな」
用はそれだけだと言えば、陸奥守は審神者の部屋に向かって去っていく。普通に接してくれたことをありがたく思いながら、その背中を見送った。
「どうやら、賭けは俺の勝ちのようだ」
「みたいだな」
賭けに負けた悔しさがじわりと身の裡に湧き上がってくるが、けれど三日月が賭けに勝ったのならば、勝った方の言うことを聞くという賭けは無効になる筈だ。この賭けは、賭けに負けて三日月に兄と呼ばされていた、という言い訳のための、口実なのだ。逆に己が勝ったら三日月に何かをさせることが出来たかもしれず、そこは多少残念でもあった。
「さてはて。では何をしてもらおうか」
そう思っていると、三日月が楽しそうにそんなことを言い出した。先ほどの寂寥さは影も形もなく、茶を持ちながら真剣に考えこんでいる。
「いやいや、待て三日月。君が勝ったのだから、この賭けは無効だろう? 言ったじゃないか、君が勝ったら、俺が賭けに負けて兄と呼ばされていたことにしてやると」
「しかし、お前は大丈夫だと言ったではないか」
「あ」
そういえばそんなことも言った気がする。己の発言も覚えていないなど、どれだけ他のものの前でにいさまと呼んだことに動揺していたのだろうか。
「そうさな」
ふむ、と三日月が一つ頷く。
「にいさまと、呼んでくれないだろうか」
遠い昔、そして三日月が顕現してから少し経った頃にも聞いた願いを、三日月は柔らかく微笑んで告げた。